目次
心理用語399例と相手の心を動かす心理用語114例、有名な心理学者80人を照らし合わせて心理用語としてご利用ください。
メンタルケア研究室のホームページで使用された心理用語の一部399例を表にをまとめています。「相手の心を動かす114例の心理用語」、「心理学の発展に影響を与えた心理学者80名」と合わせて心理用語をご利用下さい。
心理用語とは
「心理用語」とは、心理学や関連する分野において特定の概念や理論を表現し、共有するための専門的な言葉や用語のことを指します。これらの用語は、心理学の研究や理解を進めるために用いられ、特定の意味や概念を正確に伝える役割を果たします。
心理用語の特徴を挙げてみます。
- 専門性と精確性
- 心理用語は、特定の心理学的概念や理論を表現するために作られた専門的な言葉です。これによって、複雑な心理プロセスや現象を正確に伝えることができます。
- 共通の理解
- 心理用語は、専門家や学習者間で共通の理解を得るために使用されます。特定の用語がどのような意味を持つかが明確であるため、コミュニケーションが円滑に行えます。
- 体系的な理解
- 心理学は多岐にわたる分野から成り立っていますが、心理用語はこれらの分野を体系的に理解するための要素です。用語が統一された意味で使用されることで、異なる分野間の共通の基盤が築かれます。
- 知識の伝承
- 心理学は長い歴史と多くの研究に基づいていますが、心理用語は過去の知識や研究の成果を継承し、将来の研究につなげる役割を果たします。
- 学習と教育
- 学生や研究者が心理学を学ぶ際に、心理用語を理解することは基本的です。これによって、研究や理論の探求が行いやすくなります。
心理用語は、心理学の分野が進化し、新しい理論や知見が生まれるにつれて変化することもあります。したがって、常に最新の用語と概念を追跡し、注目する必要があります。
このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。
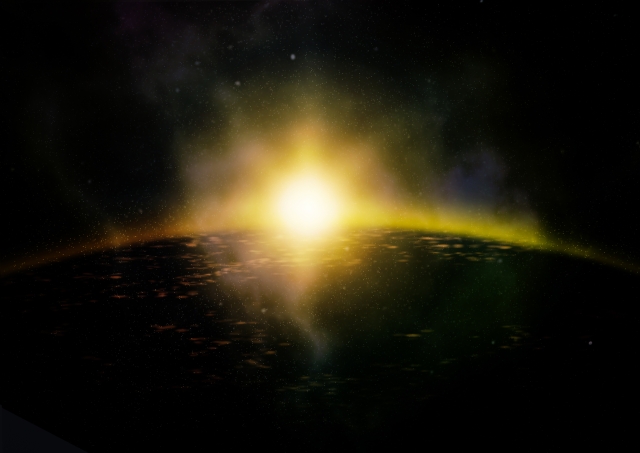
あ行の心理用語
| アイデンティティ | 自己の個性やアイデンティティー、社会的役割など、自分自身が誰であるかを把握すること。自分が属するグループや文化、価値観を認識し、それに基づいて自己理解を深めること |
| アイデンティティーの危機 | 毒親によって子供が無視され、否定され、支配されたため、自分自身についての信念や価値観が混乱し、自己同一性の危機を引き起こすことがある |
| アイヒマン実験(服従実験) | 心理学者スタンリー・ミルグラムによって行われた、服従の心理的メカニズムを調査するための実験です。 |
| 愛着 | 乳幼児期に形成される安全で信頼できる愛着の絆が健全な人格形成やストレス耐性に影響を与えるとされる概念 |
| アウトグループ・ホモジニティ効果 | ある集団(イングループ)に属する人々が、自分たちの集団外の人々(アウトグループ)を、実際よりも均質的(同質的)に捉える傾向を指します。 |
| 愛着アタッチメント | 乳幼児が本能的に母親を求め、母親も子供を求める双方向の情緒的な相互関係 |
| アドバイス・シーキン | 人々は知識や情報を得るためや意思決定をサポートするため、他者からアドバイスや意見を求める行動を指します。 |
| アクション・スリップ | 意図しない誤った行動や動作が生じる現象を指します。習慣的な動作や行動のミスなどにあたります。 |
| アタッチメント障害 | 幼少期に適切な愛着関係が築けなかったことにより、社会的相互作用の障害が生じること |
| アサーティブ | 自分の権利や意見を適切に主張し、他人との関係を尊重しながらコミュニケーションするスタイルを指します。自信と自己主張が調和した行動が特徴です。 |
| アサーティブネス | 自己の欲求や意見を相手の権利を侵害することなく誠実に素直に対等に表現すること |
| アスペルガーの研究 | ハンス・アスペルガーの研究は、後に自閉症スペクトラム障害(ASD)の概念が発展する基礎となりました。アスペルガーの記述した症状群は、後に「アスペルガー症候群」として知られるようになり、ASDの一部として分類されました。 |
| アダルトチルドレン | 機能不全家族のもとで育ち成人し、生きづらさを抱えた人 【ヒーロー】:無理に頑張る 【プリンス・プリンセス】:八方美人・忖度・従順 【スケープゴード】:生贄・丸出し 【ロストワン】:いないふりをする 【ロンリー】:殻が固く1人 【ケアティカー・リトルナース】:家以外で世話役 【イネイブラー】:家族の支え役 【プラケーター】:家族の中での慰め役・愚痴の聞き役 【クラウン(道化師)】:寂しいおどけ役 |
| アナンガム | 個人の能力とニーズと環境が一致しないと感じること |
| アフォーダンス理論 | ジェームズ・J・ギブソンによって提唱された理論で、環境が提供する行動の機会や可能性を強調し、物体や環境の特性がどのように行動を引き起こすかを考えるアプローチです。 |
| アニミズム | 非生物的な対象や自然現象にも生命や意識が備わっているという信念を指します。特に幼児や初期の人類が持っていたとされる考え方です。 |
| アパシー | 世の中で起こる事象に対して無関心、無気力になる |
| アバンドンメント | 親や養育者による心理的・身体的な放棄や無視によって、子どもが不安定な感情や行動を示すこと |
| アダプテーション障害 | 環境変化に対応することが困難である状態 |
| アルゴリズム | 特定の課題や問題を解決する手順や手法のセットを指します。計算機科学だけでなく、多くの分野で使用されます。 |
| アルバート坊や | ジョン・ワトソンとロジャー・レイナーによって行われた実験で、9ヶ月の赤ちゃんであるアルバートに対して恐怖反応を誘発するための条件付けを行った事例です。白いネズミを見ると音が鳴るようにした結果、アルバートはネズミだけでなく、似たような白いものにも恐怖反応を示すようになりました。 |
| アレキシサイミア | 感情や感情体験の認識が低いことを表す |
| アロスタシス | 状況や環境の変化に適応するための生理的および行動的な調節メカニズムを指します。ストレス応答やホルモンの変化などです。 |
| アロワー | ありのままの自分でよいと許すもの |
| アンカリングバイアス | 最初に提示された情報や数値が、その後の判断や意思決定に強い影響を与える認知バイアスです。 |
| アンダーチーブメント | 人が自分自身の能力よりも低い結果を出すこと |
| アンダーマイニング効果 | 報酬や報償を期待して特定の活動を行っていた場合、その活動に対する外部報酬が与えられると、内発的な動機付けや興味が低下する現象を指します。 |
| アンダードック効果 (負け犬効果) | 競争的な状況において、弱者や劣勢の立場にある個人やチームが逆境を乗り越えて成功を収める現象を指します。 |
| アンビバレンス | 心の中の矛盾に対する相反する両面性を持った複雑な感情 |
| アンガーマネジメント | 怒りや苛立ちの感情を適切に管理、コントロールする心理トレーニング 6秒ルール:怒りは6秒間がピークで30分でおさまる、この6秒間の間だけでも自分を抑えること |
| アンカリング効果 | 情報を受ける際に最初に提示される数値や情報(アンカー)に影響を受けて、その後の判断や評価に影響を及ぼす現象を指します。 |
| イエス誘導法 | コミュニケーションの影響力の技術の一つで、相手に「はい」と答えることを続けることで、最終的な要求に対しても「はい」と答えさせることを狙う手法です。 |
| 意志 | 意図的に行動を選択し、計画し、実行する能力やプロセスを指します。意志は人間の自己決定能力や行動のコントロールに関連しており、目標や価値観に基づいて行動を方向づける重要な概念です。 |
| 意識 | 個体が外界や内部の刺激に対して気付き、認識する心の状態を指します。 |
| いじめ | いじめは被害者に深刻な心理的なダメージを与え、不安や抑うつ、自己肯定感の低下、学校への不信感や回避、さらには自殺念慮などの問題を引き起こすことがある |
| 一次的欲求と二次的欲求 | 一次的欲求は生存に直接関連する欲求で、食事や水分のような基本的な生理的欲求を指します。一方、二次的欲求は社会的な状況や文化によって形成される欲求で、成功や承認の欲求などにあたります。 |
| イネイブラー | 依存、その他の問題行動を助長している人のこと |
| イノキュレーション理論 | 心理学とコミュニケーション研究の分野で発展した理論であり、人々の態度や信念を強化し、説得や影響に対する抵抗力を高める方法を説明します。 |
| インテーク面接 | クライエントと心理専門家との最初の面談を指します。問題やニーズを評価し、治療計画を立てるための情報収集が行われます。 |
| インファンティル・アムネジア | 幼少期に体験したことが成人期になってもほとんど記憶されていない状態 |
| インフェリオリティコンプレックス | 自分が他人に劣っていると感じる劣等感 |
| インフルエンス理論 | 特定のメッセージや行動が他者に与える影響を理解し、効果的なコミュニケーションや説得の方法を探ることを目的としています。 |
| インナーチャイルド | 人の自己概念の一部であり、成人後も残る幼い自己イメージ |
| ウィンザー効果 | 高価なワインの方が低価格なワインよりも味わいや品質が優れているという錯覚を指すような心理現象です。 |
| ヴェブレン効果 | 一般的な需要法則に反して、価格が高いほど商品の魅力や需要が高まる現象を指します。 |
| ウェルテル効果 | 自殺の模倣や自殺行動の連鎖が生じる現象を指し、特にメディア報道が自殺を詳細に取り上げた際に見られるものであり、自殺の報道や描写が他者に影響を与え、同様の行動を引き起こす可能性があることを示しています。 |
| 笑顔効果 | 笑顔が他人に与える心理的および社会的な影響を指す概念で、人間関係において非常に重要な役割を果たし、さまざまな場面でポジティブな効果をもたらします。 |
| エスカレーター効果 | 個人や集団が努力や成功を重ねることで、期待や基準が上昇し続ける現象を指します。 |
| エゴグラム | 自我状態を5つ(CP/NP/A/FC/AC)の違ったエネルギーの総和と各エネルギー量を棒グラフで示したもので、パーソナリティの特徴と行動パターンを見るもの |
| エディプスコンプレックス | 幼児期の異性の親への愛着と同性の親への反発:男児は母親を愛情の対象として父親に対し強い対抗心を抱くアンビバレントな抑圧であるが、父親の強固さから早期に終了するが、女児は長期間続く倍もある |
| MMPI | Minnesota Multiphasic Personality Inventoryは、人間の性格特性や心理的状態を評価するための標準化された尺度です。さまざまな尋ね形式の質問に答えることで、特定の心理的特性や傾向を分析します。 |
| エリクソンの催眠療法 | エリクソンは、従来の催眠療法とは異なるアプローチでは、より柔軟で個別化されたものであり、患者との協力を重視しました。エリクソンの催眠療法は、非指示的で間接的な技法を用いることが特徴です。 |
| エレクトラ・コンプレックス | 女児が父親に愛着を持つ心理ですが、女児が父親に対して性的な感情を抱くことよりも、母親との関係がより複雑であるといわれています。 |
| エンマーリング | 幼少期の過剰な依存や同一視によって、個人の自立性が著しく低下する状態 |
| おとり効果 | 選択肢に比較的価値の低い商品(おとり)を加えることで、本来の選択肢をより魅力的に見せる効果を指します。 |
| オーバージェネラライゼーション | 個別の出来事を普遍的な事実や真理として解釈してしまう認知の歪み。 例)「私はいつも失敗する。」という考え方が、一度の失敗を全体的なパターンとして認識していることを示しています。 |
| オペラント条件づけ | バラス・フレデリック・スキナーは、オペラント条件づけという学習理論を提唱しました。これは、行動がその結果によって増加または減少されるというアイディアで、行動とその結果との因果関係を強調しました。 |
| 奥行き知覚 | 物体や空間の三次元的な距離と位置を知覚する能力を指します。両眼の視差、相交視、運動の視差などが関与します。 |
| オピニオンリーダー | 他者に影響を与えることができるリーダー |
| オノマトペ効果 | 擬音語や擬態語(オノマトペ)が人の認知や感情に与える影響を指します。 |

か行の心理用語
| カインコンプレックス | 親から兄弟関係に愛情の差別を受けて養育された背景があり兄弟間の葛藤だけではなく、同じ世代の人間にも憎しみを抱くことがある |
| 快楽消失 | 快楽を感じることができなくなる症状で、食欲、性欲、趣味、社交などの日常的な活動に対する関心を失ったり、喜びや楽しさを感じなくなる場合がある |
| カウンタード | 親が子どもの自立を抑制することで、子どもの発達に悪影響を与えること |
| 確証バイアス | 自分の既存の信念や意見を強化し、それに合致する情報を選択的に受け入れる傾向を指します。逆に自分の信念に反する情報は無視されることがあります。 |
| カクテルパーティー効果 | 混雑した環境で複数の音や会話が交錯する中で、自分に関連する情報やキーワードを聞き取る能力が高まる現象を指します。 |
| 仮現運動 | 連続的に提示される静止画像が動くように知覚される現象を指します。これは、映画やアニメーションの原理とも関連しています。 |
| 学習の転移 | 一つの状況や課題で学んだスキルや知識が、異なる状況や課題へ適用されることを指します。前の学習が後の学習に影響を与えることがあります。 |
| 過剰な汎化 | 過去の一つの出来事から全体を判断してしまう傾向 例)失敗したことがあると「自分は何をやっても失敗する」と考えてしまう |
| ガスライティング | 親が子どもの認知や記憶を曖昧にし、自己の都合の良いように操作すること |
| 家族内虐待 | 毒親が子供に対して暴力や精神的虐待を加え、身体的な怪我や心的外傷などで不安やうつ病の発症などの問題が生じることがある |
| 家族療法 | 夫婦や家族が問題が明らかな場合の療法で、家族への治療援助を行う |
| カタルシス | 感情的な解放や浄化を指す心理学的な概念です。感情的なストレスや緊張が、表現や発散によって解消されることを示します。 |
| 過大評価と過小評価(虫メガネ思考) | 物事を実際よりも高く見積もったり、低く見積もったりと現実とずれた評価をすること。 悪いことには虫メガネを近づけてみるので大きく見えて、良いことは離してみるので小さく見えてしまう。 自分の短所や失敗を実際より大袈裟に考えて、上手くいったことは「こんなの当たり前だ」と過小評価してしまうこと。 |
| 学校不適応 | 学校に適応できずに不登校に至る状態であり、学童期に学校不適応に陥ると将来のキャリアや社会的適応に影響を与える可能性がある |
| カチッサー効果・カチスタ効果 | 特定の刺激(「カチッ」)が入ると、それに対応する固定化された行動パターン(「サー」)が自動的に引き起こされる現象を指します。 |
| 過度の一般化 | 過去にあった嫌だった事、まずいなと感じた事がまた起きるような危機的な心の状態 わずかな根拠をもとに「いつもこうなる」「みんなそうなんだ」とすべてのことを当てはめてしまう |
| 葛藤-コンフリクト | 葛藤は、異なる欲求や目標が競合している状態を指します。葛藤はコンフリクトに発展することがあり、個人が異なる選択肢や要求の間で決定を下さなければならない状況を生み出します。 |
| カノー効果 | 製品やサービスの特性が顧客満足に与える影響を理解し、効果的な改善策を導くための重要なフレームワークです。 |
| 可用性ヒューリスティック | 情報の入手しやすさや記憶に残りやすさに基づいて判断を行う心理的傾向です。 |
| カラーバス効果 | 特定の意識した色に関連する情報を探し求める傾向がある現象を指します。 |
| カリギュラ効果 | 制約や制限がない状況において、逆にその自由がストレスや不安を引き起こす現象を指します。 |
| カルチャーショック | 異なる文化的背景や価値観を経験することによるストレス反応 |
| 感覚遮断 | 感覚刺激が制限される状態を指します。これにより、感覚器官の情報が欠如することで、知覚や認知に影響を与える可能性があります。 |
| 感情鈍麻 | 感情を鈍くする症状で、感情の表現や体験が著しく減少する場合がある。患者は周囲の刺激に対して感じる感情が少なく、無感動や冷淡な態度をとることがある |
| 感情的決めつけ | 自分の感情を根拠に真実の証明や決めつけをしてしまう |
| 関係依存 | 女性依存や男性依存、DVなど歪んだ人間関係に依存している |
| 感情的推論 | 感情に基づいた判断をし、事実や証拠を無視する 例)「彼女が私にメールを返信しなかった。だから、私は彼女にとって価値がない存在なんだろう」と考えることがある |
| 完璧主義思考 | ひとつの妥協も許さない、例えば100点以外は0点と同じだと考える |
| 記憶 | 過去の出来事や情報を保持し、再生する心のプロセスを指します。私たちは経験したことや学んだことを記憶として蓄え、それを元に理解や判断を行い、新しい情報と結びつけることで知識や理解を形成します。 |
| 希少性の原理 | ある物や機会が限られていると認識すると、それをより価値のあるものと見なす傾向を指します。 |
| 帰属のエラー | 他人の行動や振る舞いに対して、個人的な特性よりも状況要因を過小評価したり、逆に他人に対しては個人的な特性を強調したりする認知的バイアスを指します |
| 機能不全家族 | 家庭内に対立や不法行為、虐待などが日常的に存在する家族 |
| ギバー | 惜しみなく与える人 ・自分を犠牲にして人に尽くす自己犠牲型 ・相手によって自己のかかわりを変える他者志向型 |
| 気分一致効果 | 気分や感情が思考や記憶に影響を与え、同じような気分や感情を持つ情報や出来事が強調される傾向を指します。 |
| キャリアー・インテラプション | 幼少期に家庭環境が不安定であったり貧困によって、学業や就労に影響を与えること |
| 局所論 | ジークムント・フロイトの局所論における意識の三層構造の「意識」は我々が日常的に認識している心の一部で、現在の感覚、思考、感情、願望が該当し、「前意識」は意識と無意識の中間に位置し、一時的に無意識から持ち上げられることができる精神的なコンテンツを持っています。「無意識」は、心的構造論の中で最も深い領域であり、意識から隠された状態にある精神的な要素を指します。 |
| クリプトチャイルド | 親による過保護によって子どもが自立性を獲得できずに、社会的関係に適応できない状態 |
| クレショフ効果 | 映像の編集や文脈が視聴者の感情や解釈にどのように影響を与えるかを示す現象です。 |
| クロスアディクション | 依存の対象が複数の状態 |
| 群集心理バイアス | 集団の行動や意見に無批判に従う傾向を指します。このバイアスは、集団の一員として行動することで安心感や一体感を得ようとする心理から生じます。 |
| 系統的脱感作法 | ウォルピは、恐怖症や不安障害の治療において、系統的脱感作法を開発しました。この技法は、クライアントがリラックスした状態で恐怖対象に段階的に曝露されることで、不安反応を徐々に減少させることを目指します。 |
| ゲイン・ロス効果 | 得ることと失うことに対する感じ方が異なる傾向を指し、一般的には、同じ価値のものを得ることよりも失うことの方が強く感じられるという心理的な現象を指します。 |
| 結論の飛躍 | 心の読みすぎ:他人の断片的な行動や言葉でその人はこういう人だと決めつけてしまう 先読みの誤り:根拠もない誰にもわからない先のことや将来のことを断言してしまう |
| 欠乏欲求と成長欲求 | 欠乏欲求は、マズローの欲求階層理論において基本的な生理的・安全・所属・尊重の欲求を指します。成長欲求は自己実現の欲求を含み、人々が自己の潜在能力を最大限に引き出すために努力する欲求です。 |
| ゲシュタルト療法 | ゲシュタルト療法は、ゲシュタルト心理学の理念をもとにしていますが、パールズは理論と実践を組み合わせてゲシュタルト療法を確立しています。アプローチは「今ここの気づきの体験・実習」を通して自己成長を目指す療法ですので、ゲシュタルト心理学とは弁別され、主に心理療法の領域にあります。 |
| 元型(アーキタイプ) | ユングは、元型を通じて人間の心の深層構造を探求しました。特に重視した元型には、「自己」(Self)、「影」(Shadow)、「アニマ・アニムス」(Anima and Animus)、「老賢者」(Wise Old Man)などがあります。 |
| 感情、気分、情動 | 感情は、特定の出来事や状況に対して生じる主観的な経験や反応です。喜び、怒り、悲しみ、驚き、恐れなどのさまざまな感情があります。 気分は、感情と似た概念ですが、より持続的な状態を指します。気分は一般的な感情の傾向やトーンを表現し、長期間にわたって持続することがあります。 情動は、感情や気分が外部に現れる形式を指します。つまり、感情や気分が表情、声のトーン、身体の動きなどによって他人に示されることを意味します。 |
| 見当識 | 周囲の状況に対して正確な認識と理解を持つ能力を指します。具体的には、時間、場所、人物、状況などに関する情報を正しく把握し、自分がいる状況を適切に判断できることを意味します。 |
| ゴーレム効果 | 期待や評価が低いと、その人々のパフォーマンスや能力が低下する傾向を指します。 |
| 後知恵バイアス | 出来事が起こった後にその結果を予測できたと誤って考える認知バイアスです。 |
| ゴルディロックス効果 | 最適なバランスや適切な状態が求められる心理現象を指します。 |
| 言語剥奪 | 個人が言語的な刺激やコミュニケーションを十分に受けない状況を指します。特に幼少期の言語環境の欠如が言語発達に影響を与えることがあります。 |
| 効果の法則 | ソーンダイクの理論の「効果の法則(Law of Effect)」は、ある行動が特定の結果をもたらすと、その結果が満足のいくものであれば、その行動が強化されることを意味します。 |
| 恍惚 | 現実感の低下、周囲の出来事が夢のように感じられる、自己と周囲が遠く離れているような感覚など、現実に対する感覚や認知の異常を伴う状態を指す |
| 構造論 | 心のプロセスや体験を要素に分解し、それらの関係を明らかにしようとする心理学のアプローチを指します。ウィルヘルム・ヴントによって提唱されました。 |
| 行動実験 | 検討する認知を決め、実験を通じて予想通りになるか確認する |
| 交流 | 人は言葉を送るときには、無意識の中に期待する反応がある コミュニケーションの流れであり、メッセージは言語と非言語以外にも心理的に一致して平行に流れる |
| 刻印付け | 動物が特定の期間内に特定の対象(通常は親親、または飼育者)に対して強い愛着を示すようになる現象を指します。コンラート・ローレンツによって研究され、カモやガチョウのふ化と関連付けられました。 |
| 誇大自己 | 何でも思い通りになると思っている万能感に満ちている状態 |
| 古典的条件付け | 刺激と反応の関連付けを通じて新しい反応を獲得させるプロセスを指します。イワン・パブロフのパブロフの犬の実験が有名です。 |
| 孤独感 | 他者との関係性が不足している状態や孤立している状態 |
| 個人心理学 | アドラーの「個人心理学」のなかの主要なアイデアのひとつは、「力の志向」という概念です。人々は社会的な成功や優越性を追求する欲求を持っており、それが個人の行動や心理の背後にある主要な要因であると考えました。 |
| 心の流れ | ウィリアム・ジェームズの「心の流れ」という概念は、意識が連続的に流れるように変化し、意識の中での思考や感情が連続的に出現するプロセスを指します。 |
| コミットメント | 目標や価値に対する強い関与や献身を指します。個人が自分の行動や努力を特定の目標に向けて費やすことを示します。 |
| コラム法 | 状況に対し、今の認知とは別の認知を書き出し整理するアプローチ |
| コントラスト効果 | ある対象の評価が、その対象が比較される他の対象によって影響を受ける効果を指し、対照(コントラスト)の存在が評価の基準を変えることによって生じます。 |
| コンピテンシー | 自己実現や幸福感を得るために必要な自己肯定感や自己効力感といった能力で、乳児期に獲得できる自己認識や対人関係のスキルが将来の行動特性に影響を与えるとされる |
| コンプリメンタリー | 親の自己中心的な態度によって子どもが自己肯定感の低下、自己否定、人間関係の問題を引き起こすこと |
| コンプレックス | 自己評価が低く、自分自身に対して否定的な感情を持つ傾向がある状態。例えば、身体的な外見や能力に対する不安感がある場合など |
| コンプレックス・ポストトラウマティック・ストレス障害 | 子供が毒親によって慢性的な心的外傷を受けた結果、自己認識や感情の調整、人間関係の構築などに問題を抱えることがある |
| コンプレックス・トラウマ・ディスオーダー | 時間的、頻度、重度のいずれか、もしくはそれらの組み合わせによる複雑なトラウマが発達障害、自殺企図、身体的疾患、精神疾患などを引き起こすこと |
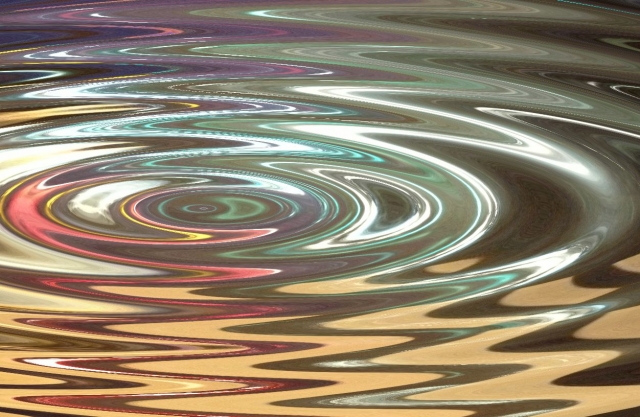
さ行の心理用語
| サーカスの像 | サーカスの像は幼少期に鎖で繋がれたまま育てられた大きな象が、成長しても鎖に縛られるイメージから逃れられない現象を指します。これは過去の経験や制約が人々の行動や信念に影響を及ぼすことを表しています。 |
| サードパーソン効果 | メディアの影響を過小評価する傾向があるという心理的現象を指します。具体的には、「他人はメディアの影響を強く受けるが、自分はそうではない」と考える傾向です。 |
| サイコドラマ | 心理的な問題を劇的な演技や役割プレイを通じて探求し、理解するための治療的手法を指します。個人やグループのセッションで行われることがあります。 |
| サバイバー | 家族内で虐待を受けて育ち成人した人 |
| サブリミナル効果 | 意識に気づかれないほどの短時間で提示された刺激が、人の思考や行動に影響を与える現象を指します。 |
| 三項随伴性 | 個人の行動とその周囲の環境および他人の影響との相互作用を示す概念です。人間の発達や学習は、個人と環境、他人との相互作用によって形成されるとされます。 |
| サンクコスト効果 | 過去に投資した資源(時間、お金、労力など)に対する感情的な執着やコミットメントが、合理的な意思決定を歪める傾向を指します。 |
| 時間の構造化 | 人はストロークが少なくなると、プラスのストロークでもマイナスのストロークでも精神的、肉体的にも満たそうとして日々の生活の中で時間の過ごし方を決めている |
| 自我意識 | 自己を認識し、自分自身について意識的に考えたり感じたりする能力を指します。これは自己の存在やアイデンティティ、思考、感情、行動などに対する認識にも影響しています。 |
| ジグソー法 | 教育の分野で使用されるグループ学習法の一つで、学生がグループで協力して、大きなトピックやテーマを理解し、学習するのに役立ちます。 |
| 指示的精神療法 | 非機能的な行動のコントロールや脱条件付けを目的としている |
| 支持的精神療法 | 強い介入的な働きを避け、長所を支持しながら現実的な問題を解決する |
| 思考 | 情報を収集し、処理し、組み合わせ、分析し、問題を解決するプロセスです。思考は知識や経験に基づいて行われ、論理的な推論や創造的な発想などさまざまな活動に関連しています。 |
| 自己開示 | 自分自身に関する情報や感情を他人と共有するプロセスを指します。コミュニケーションや人間関係の形成に影響を与えます。 |
| 自己概念 | 個人が自分自身についての認識や理解を持つ概念を指します。外見、性格、興味、価値観などに関する意識的および無意識的な認識が含まれます。 |
| 自己観 | 自己に対する認識や評価であり、幼児期に形成される自己観が自尊心や自己評価、自己受容に影響を与えるとされる |
| 自己肯定感 | 自分を受け入れて愛することができる自己評価のこと |
| 自己傷害行動 | うつ病や不安障害などの精神疾患によって、自分自身に対して傷をつけたり自傷行為を行うこと |
| 自己同一性 | 個人が自分自身を特定の特性、価値観、過去の経験などを通じて認識し、他人との違いや共通点を理解することを指します。自分のアイデンティティを形成する過程が関与します。 |
| 自己認識 | 自己と他者との区別をつけ自己イメージを形成するプロセスで、乳児期における自己認識の発達が、社会的な関係性や自尊心に影響を与えるとされる |
| 自己奉仕バイアス | 自分の成功を自分の能力や努力の結果として捉え、失敗を外部の要因や運のせいにする認知バイアスです。 |
| 自尊心 | 自尊心とは自己を肯定的に評価し自己価値感を持つことができる心の状態 |
| 自尊感情 | 個人が自分自身に対してどれだけ肯定的な評価を持つかを指します。自己評価や自信が高い場合には高い自尊感情が、低い場合には低い自尊感情が現れます。 |
| 自責思考(自己関連づけ) | 問題が起きた原因を自らに責任や落ち度があると考えるこで、他責であったとしても問題が起きた際に原因が自分を取り巻く関連や関係にあると考え自己責任にする 良くないことが起きると自分の責任にしてしまうので、罪悪感に悩まされたり他人の目が気になってしまう |
| 自伝的記憶 | 個人の人生経験や出来事に関する記憶を指します。自分自身に関連する出来事やエピソードを保持し、再生するための記憶です。 |
| 囚人のジレンマ | 協力と競争の間のジレンマを説明するために使用されます。 |
| 集団精神療法 | 異なる問題を持った集団、同一の問題を持った集団による精神分析・認知・行動療法などで、メンバー間の共感、示唆、介入、指示などの交流を行う |
| 集合的無意識 | カール・グスタフ・ユングは、個人の無意識の背後には、人類全体が共有する普遍的な無意識が存在すると考えました。 |
| 社会的補償理論 | 集団作業においてメンバーが他のメンバーの貢献度に応じて自身の努力やパフォーマンスを調整する傾向を説明する理論で、特に集団内のメンバーが能力や努力にばらつきがある場合に、他のメンバーがその不足を補おうとする行動を観察するものです。 |
| ジャム実験 | 消費者が選択肢の数が多い場合には満足度が低下し、選択肢の数が少ない場合には満足度が高まるという心理的なパターンを示唆しています。 |
| 自律訓練法 | 自己リラクゼーションやストレス軽減を促進するためのテクニックです。呼吸法やイメージリークなどを組み合わせて、身体の自律神経系を調整する効果を持ちます。 |
| 16因子人格検査(16PF) | キャッテルは、人格の構造を明らかにするために16因子人格検査(16PF)を開発しました。この検査は、性格を16の一次因子(一次特性)に分類し、個人の性格プロフィールを詳細に評価します。 |
| 馴化-脱馴化法 | 馴化は、刺激に対する反応が繰り返し提示されることによって薄れる現象を指します。脱馴化は、その後再び刺激が提示されると、反応が再び増強される現象です。この手法は、恐怖や不安などの感情を軽減するために使用されることがあります。人々が徐々に刺激に慣れ、それに対する恐怖や不安を減少させることを意図しています。 |
| ジェネレーショナル・トラウマ | 親や祖父母の過去のトラウマが子どもの発達に悪影響を与えること |
| ジェンダーディスフォリア | 人が自己の性別アイデンティティと自己の身体的性別の一致に不安を感じること |
| 初頭効果 | 情報を一度に複数提示された場合に、最初に提示された情報がより強く記憶され、後に提示される情報よりも影響を与える現象を指します。 |
| 情動的推論 | 過去の自分の経験や出来事などを踏まえて、他者が抱く情動(喜び、悲しみ、怒り、恐れなど)を推論する |
| ジョハリ・ウインドウ | 自己開示と他者からのフィードバックに基づく自己理解を促進するためのモデルです。四つの領域(公開領域、盲点領域、隠れ領域、未知領域)に情報を配置し、自己意識を向上させます。 |
| 社会的ジレンマ | 個人の利益と集団の利益との間に矛盾が生じる状況を指します。例えば、囚人のジレンマなどがあります。 |
| シャルパンティエ効果 | 物の重さを知覚するときに、視覚的な大きさがその重さの知覚に影響を与える現象を指します。 |
| 白雪姫コンプレックス | 母親が子どもの頃に虐待された経験があり、同じように子供にも虐待をしてしまい苦しんでいる |
| 人格、性格 | 人格は、一貫した行動や心理的特性の全体を指します。これは生まれつきの傾向や環境の影響によって形成され、一般的に安定して変化しにくい特徴です。 性格は、社会的な価値観や倫理的な原則に基づいて形成される行動や特性の側面を指します。性格は教育、文化、宗教、環境などの要因によって影響を受けることがあり、判断力や道徳的な選択に関連します。 |
| 心的外傷 | 体験者が深刻な心理的苦痛を引き起こす外部からの脅威や危険な出来事であり、学童期に心的外傷を経験することが、将来の心の健康や社会的適応能力に影響を与えることがある |
| 心的回転 | 物体や図形を心の中で回転させたり操作したりする認知プロセスを指します。この能力は特に空間的な課題や問題解決に関連しています。 |
| 心的構造論 | ジークムント・フロイトの人間の精神構造を形成する3つの領域である超自我は、内面にある道徳的な規範や社会的な規則を代表する心の構造であり、エスは人間の基本的な生存欲求と本能を代表していて、自我は現実と欲求や願望との間で仲介を行います。 |
| 心理社会的発達理論 | エリクソンの発達理論は、人間の一生を通じての発達を8つの段階に分け、それぞれの段階で生じる心理的課題や対立に焦点を当てていて、各段階での達成や適切な解決が、個人の心理的成長とアイデンティティの形成に影響を与えるとされています。 |
| 心的負荷 | 個人のストレス反応によって引き起こされる心的な負荷 |
| 深層演技 | 他者にとって望ましい感情を自身で生起させたり、自らの感情をコントロールする |
| シンメトリー効果 | 人間が対称的な形やデザインを美しいと感じ、好む傾向を指します。対称性は自然界でも広く見られ、人間の顔や体の対称性も美的魅力に影響するとされています。 |
| 心理教育 | 専門的な立場からわかりやすく、症状のメカニズムや診断、治療方法など説明する |
| 心理的安全性 | 個人が自分自身を表現し、意見やアイデアを提供する際に、恐れや制約を感じることなく受け入れられる環境を指します。チームや組織内でのコミュニケーションや協力に重要です。 |
| 心理的拘泥現象 | 過去の信念や意見に執着し、それらを変えることを難しく感じる心理的な現象を指します。 |
| 心理性的発達理論 | ジークムント・フロイトの提唱した理論は、人間の心理的成長が特定の身体部位(性的エネルギーの源、リビドー)に焦点を当てた「口唇期」「肛門期」「男根期」「潜伏期」「性器期」の5つの段階を通じて進むというものです。 |
| 心理的リアクタンス | 自分の自由や選択が制限されると、その制限に反抗し、逆にその行動や選択を強化する傾向を指します。 |
| 心理的離乳 | 仕事やストレスから一時的に離れ、リラックスや回復するプロセスを指します。心の健康とバランスを保つために重要です。 |
| 集団極性化 | 集団内のメンバーが議論や相互作用を通じて、グループの立場や意見がより極端な方向に傾く現象を指します。これにより、個人の意見が集団の平均的な意見よりも強化されることがあります。 |
| シンデレラコンプレックス | 女性の潜在意識にある男性に高望みや理想を求める依存的願望 |
| 心理ゲーム | 理性的な気づきがないため明瞭で予測可能な結果に向かって進行する。この予測は繰り返し人間関係を拗らせたり、非建設的な結果を招いたりする後味の悪い交流パターンとなる 家族や親しい中など特定の対象と条件が揃うと相補的・裏面的交流で自我状態の転換とともに終わるのが特徴で密度の高いストロークの交換である |
| 推理の飛躍(恣意的推論)(結論の飛躍) | 正当な証拠もないのにガティブな結論を自分勝手に導き出す。 良くない結果を先読みしたり、相手の顔色からその人の考えを深読みしてしまう |
| スキーマ療法 | 個人の問題や苦悩の根源にある心理的スキーマ(構造化された信念や思考、感情、行動のパターン)を理解し、変容を促すことを目的としている |
| スタンフォード監獄実験 | 人々が特定の役割や環境に影響されて行動する可能性を示した重要な研究とされています。 |
| ステレオタイプ | 特定のグループやカテゴリに対する固定的な偏見や一般化された信念を指します。しばしば根拠のない情報に基づいて形成されることがあります。 |
| ストループ効果 | 単語の意味に対応する色の情報が異なる場合に、色の情報を正確に認識するのに時間がかかる現象を指します。 |
| ストレス | 生活や仕事などの外的な要因によって引き起こされる、身体的・心理的な緊張状態。継続的にストレスがかかると、心身に様々な不調が生じることがある |
| ストレス・コーピング | ストレスや困難な状況に対処するための戦略やアプローチを指します。問題解決、感情の調整、社会的サポートなどがストレス・コーピングの方法です。 |
| ストレンジシチェーション法 | 幼児のアタッチメント(愛着)を評価するための心理学的評価方法です。母親との分離と再会、他の人物との対面などを通じて、幼児の行動を観察することで愛着のパターンを分析します。 |
| ストローク | 相手の存在を認めて心理的・身体的・物理的に働きかけ、他者に与える認識、注意、反応刺激の一単位である |
| スチューデント・アパシー | 自分の勉学(社会人なら本業)以外は熱心にできるが、勉学だけはできない状態 |
| 「すべき」思考 | 何かやろうとするときに「~するべき」「~するべきでない」と固定的な考え方をする。 「すべき」に縛られて生活が窮屈になったり、自分や他人の失敗を許せずにプレッシャーや怒りを感じやすくなってしまう 「他人に弱音を吐くべきでない」と考えて、辛いことがあっても誰にも言えず我慢してしまい、自身の限界値を超えてしまう |
| スノッブ効果 | 一般的な人気や一般的な選択肢に反対して、特に高級な、希少な、または他の人々とは異なる選択肢を好む傾向を指します。 |
| スポットライト効果 | 他人から見られる自分の行動や立ち振る舞いの注目や評価が実際よりも大きいと感じる傾向を指します。 |
| 刷り込み | 人々の意識や信念を意図的に変えるために行われる心理的な操作や洗脳のことを指します。通常、強制的な状況や情報の絶え間ない提示によって行われます。 |
| スリーパー効果 | 最初は影響が少なく見える情報やメッセージが、時間の経過とともに影響を高める現象を指します。 |
| 精神力動的精神療法 | 無意識の中に押さえ込まれた欲動を自由連想法により、葛藤を明らかにし症状を改善する |
| 性同一性 | 個人が自己の性別について感じる自己認識やアイデンティティーが、その人が生まれた時に割り当てられた生物学的な性別と一致しない場合があり、学童期の性同一性には、長期的な性同一性障害という状態と一時的な性的好奇心や探求という状態の両方が含まれることがある |
| 成功不安 | 成功することに対して不安や恐れを感じる現象を指します。自己評価や社会的期待とのギャップが引き起こすことがあります。 |
| 正常性バイアス | 人々が非常事態や危機を認識せず、常に事態が正常であるとの思い込みを持つ傾向を指します。これにより、非常時の行動や対処が遅れることがあります。 |
| 生存者バイアス | 成功した事例や生き残った事例に焦点を当て、それらの共通点や要因だけを分析することで、失敗した事例や脱落した事例を無視する認知バイアスです。 |
| 説得的コミュニケーション理論 | 態度や行動を変えるためのコミュニケーションプロセスを研究する理論で、メッセージの構造、伝達者の信頼性、受け手の特性、状況などがどのように影響するかを分析します。 |
| セルフフルフィリング・プロフェシー | 自己成就予言は、人々が持つ予期や期待が、その予期された結果を実現するような行動や反応を引き起こす現象を指します。 |
| 選択的抽象化(心のフィルター) | 物事全体の中から悪い部分の方にだけに目が行ってしまい、良い部分は除外して物事を捉える |
| 選択的注意 | 膨大な情報の中から特定の刺激や情報に対して意識的に注意を向ける現象を指します。 |
| 選択的注意バイアス | 特定の刺激や情報に対して過度に注意を払い、他の情報を無視する傾向を指します。 |
| 漸進的筋弛緩法 | 緊張やストレスを軽減するためのリラクゼーション法です。筋肉を順番に収縮させてから緩めることで、身体の緊張を解放し、心身のリラックスを促進します。 |
| 全能感 | 幼児は自分自身が全能的であると感じていて、自分自身の行動や思考が全ての結果を生み出すと信じている |
| 早期環境 | 乳児期に経験した育児環境が、その後の発達や行動に影響を与えるとされる概念で、親や保育者との関係性、愛着形成、ストレス耐性に悪影響を与える |
| ソーシャル・コンフォート理論 | 社会心理学における概念の一つで、人々が社会的な状況でどのように感じ、振る舞うかを説明する理論で、人々の行動や感情が、社会的な状況によってどのように影響されるかを理解しようとするものです。 |
| ソーシャル・サポート | 他人からの感情的な支援、情報、助言などを通じて、個人の健康や幸福を促進する役割を果たす関係を指します。 |
| ソーシャル・ネットワーク | 個人や組織、グループなどが関連づけられた社会的なつながりのパターンを指します。友人、家族、同僚などにあたります。 |
| 相補的交流 | 発信者と受信者の言葉と非言語のメッセージが一致していて期待通りの言葉が戻ってくること。お互いに求めている反応のように相互補完的交流である |
| ソシオメトリー | 集団内の人間関係や社会的つながりを分析する方法を指します。集団内での個人間の関係性を理解するために使用されます。 |
| 損失回避バイアス | 利益よりも損失をより強く避けようとする認知バイアスの一種です。 |

た行の心理用語
| 体験的精神療法 | 感情表現の促しで、共感的理解を体験することで症状を和らげる |
| ダイアナコンプレックス | 女性の背景に男らしくなりたい、男性に負けたくないなどで男根羨望を強く感じ男性でありたいと感じている |
| 対象喪失 | 愛する人や重要な対象の喪失に伴う感情的な経験を指します。喪失が適切に処理されない場合、悲しみや喪失感が持続することがあります。 |
| 対人認知 | 他人との関わりやコミュニケーションに関する認知プロセスを指します。他人の感情や意図を理解し、対人関係を築く際に重要です。 |
| タイム・プレス効果 | 時間的制約が増加すると、人々がより迅速に意思決定を行ったり、問題解決を試みたりする傾向があることを示します。 |
| タイム・ディレイ効果 | 特定の行動や刺激がその効果を発揮するまでに時間の遅れが生じる現象を指します。 |
| ダニング・クルーガー効果 | 自己評価の誤りに関する心理現象で、自分の能力やスキルを過大評価してしまう傾向がある人より、高い能力やスキルを持つ人は自己評価が低いという現象を指します。 |
| 耐性領域 | レベルや能力を向上させるために最適なレベルを指します。この領域では、個人が自身の能力を拡大し、新たなスキルや知識を習得するための適切なサポートが提供されます。 |
| 脱中心化 | 個人が自分の視点や視野を広げ、他人の視点や視野を考慮する認知的スキルを指します。特にピアジェの認知発達理論において言及される概念です |
| 多元的無知 | 意見や感情が他の人と異なると認識しながらも、圧力や風潮を感じるなどで自分と異なる意見の方を多くの人々が受け入れていると勘違いする現象を指します。 |
| ダブルバインド | 矛盾する要求や情報のことで、どちらの選択肢を選んでも困難な状況に追い込まれる心理的な状況を指します。 |
| 短期記憶 | 一時的に情報を保持し、操作するための記憶の部分を指します。情報は時間とともに失われやすい特徴があります。 |
| 単純接触効果 (ザイオンス効果) | 異なる社会集団と直接的な接触を持つことで、対立や偏見を減少させる現象を指します。 |
| 知覚 | 外界からの情報を感じ取り、その情報を解釈して理解する心のプロセスを指します。私たちは五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)を通じてさまざまな刺激を受け取り、それに対して意味を持たせ、自分の現実の理解を形成します。 |
| 遅延反応 | 即時の報酬や快楽を我慢して、将来的な報酬や目標を達成するために努力する能力を指します。これは自己統制や長期的な計画の一部として重要です。 |
| 知能 | 新しい情報を学び、問題を解決し、環境に適応するための能力を指します。知能は多様な認知的スキルと能力の組み合わせによって表れます。一般的に、知識の取得や応用、論理的思考、問題解決能力、言語理解、空間認識などが知能の一部とされます。 |
| 長期記憶 | 情報や経験を長期間にわたって保持する記憶の部分を指します。知識、経験、出来事などにあたります。 |
| 吊り橋効果 | 高所恐怖症のような強い感情的な状態が、新たな人間関係を築く際にポジティブな影響を与える現象を指します。 |
| ツァイガルニク効果 | 未完了のタスクや不完全な情報が、人々の意識や注意を引きつけ、記憶に留めておく傾向を指します。 |
| ディアルーゲンス | 社会的接触の欠如によって引き起こされる孤独感、現実感の喪失や非現実的な感覚の体験 |
| ディアボリカル・アイデンティティ・シンドローム | 毒親によって子供が否定され、無力感や劣等感を抱えた結果、社会的に問題のある行動をとるようになることがある |
| テイカー | 自分の利益を優先させる人 ・与えるより受け取りが多くなるように行動する ・長期的に見てどれだけ受け取れるかで行動を変える |
| ディスコンフォート | 心理的に不快な状態であり、何かしらのストレスを感じる状態。不安や悲しみ、怒り、焦りなどが原因で生じることが多い。 |
| ディドロ効果 | 一つの新しいアイテムや所有物が持ち主の他の所有物との調和を乱し、連鎖的に新しい物品の購入を引き起こす現象を指します。 |
| デルボーフ効果 | 円形の図形の中に別の円を描いたり、環状の図形の中に別の環を描いたりすることで、その内側の円や環の大きさが周囲の環境によって異なるように知覚されることを観察しました。 |
| 敵意帰属バイアス | 他者の行動や意図を、過度に敵対的・悪意的だと解釈してしまう認知バイアスです。被害妄想的観念とにていて、特に曖昧な状況で、他人の行動が自分に対して敵意を持っていると認識してしまう場合に発生します。 |
| テンション・リダクション効果 | 不安やストレスを軽減するために、気晴らしや娯楽を求める傾向を指します。 |
| 洞察的精神療法 | 無意識的な葛藤の洞察を促し、精神症状を和らげる |
| 動因と誘因 | 動因は、生体内の不快な状態を解消するための内部的な刺激や欲求を指します。誘因は、外部からの刺激や情報であり、動因を引き起こす要因です。 |
| 投影バイアス | 自分の現在の感情や思考、信念を他人も同じように感じたり考えたりしていると誤って推測する認知バイアスです。 |
| 同化と調節 | 新たな情報や経験を既存の認知構造に適応させることを指します。調節は、新しい情報に基づいて認知構造自体を変化させるプロセスを指します。ピアジェの発達理論における概念です。 |
| 同調 | 他人の意見や行動に合わせる傾向を指します。集団内での社会的圧力や規範に従い、自身の行動を調整することがあります。 |
| 同調効果 | 他人の意見や行動に合わせることを指す心理現象です。他人の行動や意見に従うことで、自己同一性の維持や社会的な調和を図ることがあるため、同じ行動や意見をとることがあります。 |
| トラウマ | 身体的・精神的な苦痛や苦悩を引き起こす極度のストレス体験であり、乳幼児期にトラウマを経験するとその後の生活に悪影響を及ぼすことがある |
| 泥棒洞窟実験 | 個人の行動が倫理的なジレンマによって影響されることを示す重要な実験です。 |

な行の心理用語
| 内的対象関係 | メラニー・クラインは、対象関係論の発展で幼児がどのようにして他者(対象)との関係を構築し、それが心の発達にどのように影響するかを詳細に研究しました。 |
| ナルシシズム | 親の自己中心的な態度によって、子どもが自己肯定感の低下、自己否定、人間関係の問題を引き起こすこと |
| 二極思考 | 事物や人物を「良いもの」「悪いもの」の2つに分けて考え、中間的な見方ができない。 例)「この仕事は完璧でなければならない。完璧でなければ、私は失敗者だ」と考えることがある。 |
| ニヒリズム | 価値や意味を否定する思想や哲学 |
| 認知行動療法 | アーロン・ベックは、うつ病患者の思考パターンを研究する中で、否定的な自動思考が感情や行動に大きな影響を与えることを発見しました。 コラム法・問題解決法・認知再構成法・系統的脱感作法・暴露反応妨害法・活動活性化技法・モデリング法、マインドフルネスなどがある |
| 認知発達理論 | ピアジェの理論は、子供が幼少期から青年期にかけて、認知能力が段階的に発達し、異なる認知的構造を獲得するという考え方に基づいています。具体的には、感覚運動期、前操作期、具体操作期、形式操作期の4つの段階を示しました。 |
| 認知的不協和理論 | 自分の持つ信念や態度と矛盾する情報や行動に直面した際に、不快な状態(認知的不協和)を感じ、その状態を解消しようとする心理現象を指します。 |
| 認知の歪み | 物事の捉え方に歪みや偏りがある |
| 認知モデル | 状況における感情や行動は、その状況に対する意味づけや解釈である「認知」と関係がある。どう認知するかによって感情や駆動は変わる |
| ネームレター効果 | 自分の名前のイニシャルを含む文字に対して、他の文字よりも好意を持つ傾向を示す現象です。 |
| ネガティビティ・バイアス | ネガティブな情報や出来事に対してポジティブなものよりも強く反応し、記憶に残りやすいという心理的傾向を指します。 |
| ネグレクト | 親が子どもの基本的な生活必需品を提供しない、無視するなどの不十分な育児を行う状態 |

は行の心理用語
| パーソナライゼーション(個人化) | 自分自身に対する責任や評価を、実際よりも大きく見積もってしまう認知の歪み。 例)友達が会いに来なかったのは自分のことが嫌いだからだと思い込んでしまう。 |
| パーキンソンの法則 | 仕事やタスクの遂行に必要な時間が、その仕事の難易度や重要性ではなく、与えられた時間加減の範囲内で膨張する傾向を指します。 |
| ハード・ツゥー・ゲット | あえて接近の可能性を減少させたり、関心を持っている対象を手に入れにくくすることで、その対象への興味や関心を高める心理的な戦略を指します。 |
| バーナム効果 | 漠然とした、曖昧な誰にでも該当しそうな表現や記述が自分のことを言い当てられているように感じる現象を指します。 |
| バーンアウト | 仕事や学業などの長期間にわたるストレスや負担が蓄積し、身体的・感情的・精神的な疲労や無力感、意欲の低下などが生じる状態を指します。特に専門職や介護者などで見られることがあります。 |
| バイオフィードバック | 生体内の生理学的な活動を計測し、その情報を個人に提供するプロセスを指します。心拍数、筋肉の緊張などの生体情報を用いて、自己調整やリラクゼーションのトレーニングに活用されます。 |
| バイオリズム | 人間の身体的・感情的・知性的なサイクルが周期的に変動するとする理論を指します。身体的、感情的、知的バイオリズムが提唱されていますが、科学的根拠は限られています。 |
| バイオロジカル・ファクター | 親と子どもの関係に生物学的要因が関わっている場合、その人の行動や精神状態に影響を与える要因のことを指しますが、遺伝的な影響、脳内物質や神経伝達物質のバランス、身体的な健康状態、発達段階などが含まれる |
| 破局化思考 | 一つのミスを取り返しの付かない決定的な破滅と考える |
| 非対称な洞察の錯覚 | 他者についての洞察や理解が自分の方が深いと信じる一方で、他者が自分を理解する力を過小評価する認知バイアスです。 |
| 発達課題 | 年齢に応じた心理的な成長に必要な課題を未解決のまま成長してしまうと、その後の心理的な問題につながることがある |
| バタフライ効果 | 繊細で敏感な子供が毒親によって常に怒られ、責められ、否定された結果、後に人生で起こる些細な出来事でも大きなストレス反応を引き起こす可能性がある |
| バックファイア効果 | 情報や証拠が提示されても、それが信念や意見に反する場合に、人がその信念をさらに強固にする現象を指します。 |
| 発達加速現象 | 一部の子どもたちが同年齢の平均よりも早く発達する現象を指します。例えば、特定の認知能力や知識分野において他の子供よりも優れていることがあります。 |
| 暴露法 | 警戒反応がしても、そこを避けず積極的に味わうことで反応の変化に注目する |
| パブロフの犬 | イワン・パブロフによって行われた実験で、犬の消化液分泌を調べる際に偶然発見された現象です。ベルの鳴る音(中立刺激)とエサを提供すること(非中立刺激)を繰り返し結びつけることで、ベルの音だけで犬が消化液を分泌する反応を示すようになったという実験です。 |
| パラノイア | 信念や感情、行動が他者によって監視され、支配されているとの不合理な恐怖 |
| バランス理論(均衡理論) | 自分の信念や態度が一貫性を持つように調整しようとする傾向があるとされています。 |
| ハロー効果 | ある特定のポジティブな特徴や評価が、その人の他の側面にも好意的な印象を与える現象を指します。 |
| バンドワゴン効果 | 他人が何かを支持・賛同していると知った際に、その人々に同調することが増える現象を指します。 |
| バンドゥラの社会学習理論 | 観察学習は、対象とする人々の行動や結果を観察し、それを自分の行動に統合するプロセスです。 |
| バンドワゴン効果 | 多くの人が特定の行動や考え方を支持している場合に、自分もその流れに乗ろうとする心理的傾向を指します。 |
| PM理論 | 自分の状態を制御するためにどのように行動を選択するかを説明する枠組みで、感覚入力と参照モデルの間の差異を最小限にするために、行動を調整し、自己の目標達成を追求します。 |
| ピーク・エンドの法則 | ある経験やイベントを評価する際に、その経験やイベントの最も高い点(ピーク)と終了時点(エンド)を基にして、全体の印象や感情を形成する心理現象を指します。 |
| ピーク・シフト効果 | 心理学および行動学の分野で観察される現象で、学習理論に関連していて、動物や人間が刺激の違いを学習する際に、学習した反応が元の刺激から遠ざかることを指します。 |
| ピグマリオン効果 | 他人からの期待や信念が、その人の行動や能力に影響を与える現象を指します。 |
| ビデオ・フィードバック法 | 振る舞いをビデオに録画し、自身のイメージと実際の差異について振り返る。他者からのフィードバックも可能 |
| ビッグ・ファイブ | 人間の性格特性を表す五つの基本的な要因(外向性、協調性、誠実性、感情起伏、開放性)を指します。これらの特性は、人々の性格を評価するための主要な枠組みです。 |
| 批判的期 | 幼児期の4~6歳頃に訪れるもので自己中心的な思考から抜け出すための発達段階であり、この時期をうまく乗り越えられないとその後の対人関係や問題解決能力に影響を与えることがある |
| 批判的思考 | 情報やアイデアを評価し、論理的に考える能力を指します。証拠に基づき主張を判断し、偏見や誤った情報を排除して合理的な結論を導く能力です。 |
| ファミリアリゼーション | 家族の文化や価値観を受け入れ身につけることであり、幼児期のファミリアリゼーションが、将来の価値観や生き方に影響を与えるとされる |
| フェアネス理論 | 人々の行動や意思決定における「公正さ」や「公平さ」への重要性を指摘する理論で、自分自身や他者に対して、公正で公平な扱いを期待し、その期待に応じて行動します。 |
| ブーメラン効果 | 他人の試みが逆効果となり、本来の意図とは反対の結果をもたらす現象を指します。 |
| 分離-個体化理論 | マーガレット・S・マーラーの分離-個体化理論は、乳幼児の健全な発達における母子関係の重要性を強調し、乳幼児が母親から心理的に分離し、自分自身を個別の存在として認識する過程を1カ月〜36カ月を段階的に捉えたものです。 |
| ペアレンタル・アリエネーション | 離婚や親の対立などが原因で、一方の親が子供との関係を深めるために意図的に他方の親を排除する行動を指します。 |
| ホーソン効果 | 研究対象者が観察されていると感じることで、その行動が変わる現象を指します。 |
| フォールス・コンセンサス効果 | 自分の考えや信念が、他の人によっても共有されていると過大に見積もる傾向を指します。 |
| 孵化効果 | 人々が自分たちが成し遂げたものに対して過度の評価を持つ傾向を指します。過去の努力や投資に基づいて、その成果物やアイデアを高く評価しやすくなる現象です。 |
| フット・イン・ザ・ドア・テクニック | まず小さな依頼や要求を行い、その後に大きな依頼や要求を行うことで、対象となる人の同意や協力を得やすくする心理的手法を指します。 |
| プライミング効果 | 一度特定の情報や概念が意識に浮かぶと、それに関連する他の情報や概念が活性化されるため、その後の情報の受け入れや評価に影響を与える現象を指します。 |
| プラシーボ効果 | 実際には治療効果のない物質や手法が、被験者の信念や期待によって治療効果を示す現象を指します。 |
| フラストレーション | 目標達成や欲求の満足が妨げられることによって生じる不快な感情を指します。達成を妨げる障害や困難がある場合に経験されることがあります。 |
| フリー・ライダー効果 | 集団活動や公共の提供において、他人の貢献や努力に依存して自分は貢献しないで利益を享受する現象を指します。 |
| ブルースペース効果 | 青い環境、特に水のある風景が人々の心理的および生理的健康に与えるポジティブな影響を指します。 |
| フレーミング効果 | 情報が提示される方法や文脈によって人々の判断や意思決定が影響を受ける現象です。同じ情報でもポジティブな言い回しとネガティブな言い回しで反応が異なる場合があります。 |
| プロスペクト理論 | ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)とアモス・トヴェルスキー(Amos Tversky)によって提唱された心理学の理論で、人々は損失と利得を異なる方法で評価し、損失回避の傾向が強いとされています。 |
| 噴水効果とシャワー効果 | 情報の伝播や共有のパターンを表現するための概念です。噴水効果は急速な情報の広がりを示し、シャワー効果はゆっくりとした広がりを示します。 |
| ペアレンタル・アリエネーション | 毒親が子供を自分の味方に引き入れるために、他方の親や家族との関係を妨害することによって、子供が親や家族から遠ざかることがある |
| ベビーフェイス効果 | 子供のようなかわいらしい顔立ちや特徴を持つ人が、一般的により親しみや好意をもって受け入れられる傾向がある現象を指します。 |
| 返報性の原理 | 他人から受けた恩恵や好意に対して、同じ程度の恩恵や好意を返す傾向があるという心理的な原則を指します。 |
| 表層演技 | 望ましい感性を装い表情やしぐさを実際の感情とは異なる状態に変化させる |
| 漂白 | 悪い出来事や状況を良いものとして認識する傾向 例)虐待やいじめを「自分を鍛えるための良い経験だった」と考えてしまう |
| フィルタリング | 特定の出来事や情報を選択的に取り上げ、他の情報を無視してしまう認知の歪み 例)失敗や批判的なコメントだけを選んで気にしてしまい、自分にとってのポジティブな出来事を見逃してしまう |
| ブックエンド効果 | シリーズやセット、プロジェクトの始まりと終わりを強調することで、全体をより印象的にする心理的効果を指します。 |
| プレジャーシーキング | 新しい刺激や興奮を求める行動傾向であり、学童期にプレジャーシーキング行動が高まると、将来のリスク行動や問題行動につながる可能性がある |
| プルキンエ現象 | 夜間の照明条件下で、青い対象よりも赤い対象の方が明るく見える現象を指します。これは、人間の視覚系の特性に関連しています。 |
| 文脈効果 | 文脈効果は、情報や刺激の理解や記憶が、その文脈や環境によって影響を受ける現象を指します。情報の提示や評価が周囲の状況に影響されることがあります。 |
| ホーソン実験 | 単に物理的な条件だけでなく、人間関係や組織文化などの要因が労働者の行動に影響を及ぼすことを示す重要な事例です。 |
| 防衛機制 | 環境への適切な対応を支援するための心理的なプロセスです。問題解決や環境への適応に役立つ方法です。 |
| 傍観者効果 | 多くの人々が危機的な状況に対して介入しない傾向を指します。他人がいる場面で自分が助ける必要がないと錯覚しやすく、結果的に行動が遅れることがあります。 |
| ポジティブ心理学 | マーティン・セリグマンは、従来の心理学が問題解決や障害の克服に焦点を当てるのに対し、ポジティブ心理学は人々の幸福、喜び、幸福感、クオリティ・オブ・ライフに注目するというアプローチを提唱しました。 |
| ポジティビティ・バイアス | 経験や情報を評価する際に、ポジティブな側面や感情を過大評価し、ネガティブな側面を過小評価する傾向を指します。 |
| 保有効果 | 自身が所有している物品や資産に対して、それらの価値を高く評価する傾向がある心理的現象を指します。 |
| ホメオスタシス | 生物の体内環境を一定の範囲内に保つ調節メカニズムを指します。例えば、体温や血糖値などが一定の範囲で維持されるプロセスです。 |

ま行の心理用語
| マインドリーディング | 相手の気持ちや思考を想像し理解することであり、幼児期に親や周囲の人々からの関心や共感を経験することが、マインドリーディング能力の発達につながるとされる |
| マウス・エイムス・マン | 乳児期の研究者として知られるジョン・ボウルビィによって提唱された概念で、乳児期の愛着形成における行動パターンを表し、安心して探索行動をするか、不安定で依存的な行動をするか、回避的な行動をするか、抵抗的で敵対的な行動をするかが分類される |
| マイナス思考(プラスの否定) | プラスの出来事であっても否定してマイナスに考える。良いことが受け止められなく、逆に悪いことが起きそうだと考える |
| マイナス(否定的)のストローク | 受け手が決めるものであるが、脅す、貶す、嫌み、危害を与えるなどの方法で相手に反応させ、ストロークを満たそうとする 否定的な言葉でも存在していることの証となるので、ストロークがない(無視される)よりずっと良い |
| マグニファイ(誇張) | 問題や懸念事項を過剰に大きく見積もってしまう認知の歪み。 例)試験に落ちたことが、将来において全てを台無しにしてしまうと思ってしまう |
| マザー(ファーザー)コンプレックス | 母親(父親)に対して息子(娘)が執拗な執着や愛着の依存関係を持ち続けている |
| マターナル・デプリベーション | 幼児期に母親の愛情やケアが不足することによって引き起こされる心理的な問題を指します。ジョン・ボウルビィのアタッチメント理論において重要な概念です。 |
| マッチャー | 損得のバランスを考える ・相手によって自己のスタンスを変える ・相手がギバーでもテイカーでも与える量と受け取る量の一致を目指す |
| マッチングリスク意識 | 選択肢を比較し、最適な選択をする際に、リスクや不確実性をどのように評価するかに焦点を当てた概念です。 |
| マッチング・ハイポセシス | 自分自身と類似した他者と関係を築く傾向があるという仮説を指し、自分と類似した他者との関係を好み、そのような関係がより良好で安定したものとなるとされています。 |
| マーフィーの法則 | 「失敗する可能性があるものは、失敗する」「なぜか必ず不運な方が起こる」という意味のことです。 |
| マム効果 | 他者に対して悪いニュースや否定的な情報を伝えることを避ける傾向を指します。 |
| マンデラ効果 | 集団で同じように誤った記憶を持つ現象を指します。 |
| 3つの未来 | ・避けたい未来・予想される未来・望む未来 |
| 3つのシナリオ | ・最悪シナリオ・現実的シナリオ・最高シナリオ |
| 3つ(3徴)の否定的認知 | ・他人(世界)のこと・自分(過去)のこと・未来のこと |
| 3つの避ける怒りの感情 | ・攻撃・破壊・衝動 |
| 3つのコミュニケーション・パターン | ・アグレッシブ(他人を尊重していない)・ノンアサーティブ(自分を尊重していない)・アサーティブ(自他尊重) |
| 3つのストレス・コーピング | ・受容・共感・自己一致 |
| 3つのステイト・マネージメント | ・ポジティブイメージ・未来のありたい自分・表情フィードバック |
| 3つの脳の使い方の癖観察 | ・見えるもの(視覚)・聞こえるもの(聴覚)・身体で感じるもの(体感覚) |
| 3つのコラム | ・状況・思考・感情 |
| 3つの過ちへの行い | ・謝罪・原状回復・再発防止策 |
| 3つの勇気 | ・不完全であることを認める(受け入れる)・失敗をする勇気(チャレンジ)・過ちを認める勇気 |
| 3つの自分と相手のバランス | ・権利・義務・要求 |
| 3つの脅威への反応 | ・服従(麻痺)・回避(逃げる)・過剰補償(闘う) |
| 3つの無意識、意識の考え方 | ・無意識と意識は対立している(フロイト)・無意識と意識は同じ方向に向いている(アドラー)・無意識と意識は共同作業ができる(ユング) |
| 3つの心の状態 | ・理性的な心・賢い心・感情的な心 |
| ミラーリング効果 | 他人の行動や姿勢、表情などを模倣する現象を指します。つまり、他人の振る舞いや態度に自然と合わせて同じような行動をとることを指します。 |
| ミラーの法則 | 人間の短期記憶の容量に関する研究を行いました。ミラーは人間の短期記憶の容量は約7つのアイテム(プラスマイナス2)に限られていると主張し、この法則を提唱しました。 |
| ミルグラムのオベディエンス実験 | 心理学者スタンリー・ミルグラムによって1961年に行われた社会心理学の実験です。この実験は、人々が権威的な指示に従う傾向がどれほど強いかを調査しました。 |
| メサイアコンプレックス | 人を救済する誇大妄想を持つ背景には、自己満足を得ようとすることや自分が劣等感を埋めるための生きづらさを抱えている |
| メタ認知 | 自分自身の思考や学習プロセスに対する認識や理解を指します。自分の思考を監視し、効果的な学習戦略を選択するための能力です。 |
| メラビアンの法則 | アルバート・メラビアンによって提唱されたコミュニケーションの理論で、感情や態度の伝達において、言葉のみがコミュニケーション全体の意味の大部分を占めるわけではなく、音声のトーンや非言語的な要素(身振りや表情)が重要な役割を果たすことを指摘しています。 |
| メンタルブロック | 創造的な思考や問題解決能力が妨げられる状態を指します。新しいアイデアや解決策が浮かばない、情報の整理が難しいなどが含まれます。 |
| 妄想的解釈 | 現実的でない、超自然的な解釈をする傾向。 例)自分の願い事が叶うように祈るだけで実現すると信じる |
| 妄想分裂ポジション | 自己にとって思い通りにならない状況でその不快さを全て相手の非とみなし怒りや攻撃を爆発させている状態 |
| モデリング | 他人の行動や態度を観察し、それを模倣することで学習するプロセスを指します。特に、子どもが大人の行動を模倣して学習する場面で重要な概念です。 |
| モラトリアム | 個人がアイデンティティ形成の過程で一時的に探索や試行を行う期間を指します。例えば、学業や職業、価値観などについて選択を行う過程にあたります。 |
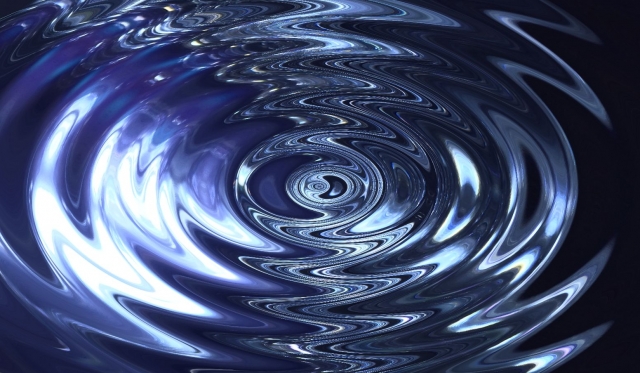
や行の心理用語
| 野生児研究 | 野生や孤立状態で育った子どもたちの発達や社会化についての研究を指します。野生児が言語や社会的スキルを習得できない場合、人間の発達にどのような影響があるかを理解するために行われます。 |
| 良い面の無視(色メガネ思考) | 良い面があるのに、目に入らず(無視して)そうでないことばかりに意識を集めてしまう ネガティブな色メガネを通して物事を見るので、何事もネガティブに見えてしまうこと |
| 幼児的万能感 | 自分はどんなことでもできる、何にでもなれるというような子供の頃の現実離れした夢や理想を抱いている ・幼児期から青年期、大人になる過程において乗り越えるべき発達課題を乗り越えていないために生きづらさの原因になっていて、内心は不安でいっぱいになり幼児的万能感にすがるしかないという問題を抱えている ・ベースには愛情や期待が強かった親でもあり、親の保護や支えを自分の実力と認知している可能性がある |
| 抑うつポジション | 自己と他者との区別ができて、罪悪感や自己反省、さらに相手に対する思いやりが発達していく状態 |
| 遊戯療法 | 遊戯療法は、世界初の児童分析家であるヘルミーネ・フーク=ヘルムートが「子どもの精神分析には遊びが必要である」と提唱したことから始まりました。メラニー・クラインは、子供が遊びを通じて無意識の感情や葛藤を表現することを発見し、遊びを分析の手段として用いました。これにより、言葉を使えない幼い子供たちの心理を理解することが可能になりました。 |
| 欲求階層理論 | アブラハム・マズローが考案した自己実現論の「マズローの欲求5段階説」は、低次元の欲求が満たされることによって一つ上へと欲求の階段を上っていくという解釈です。 |
| 予測の誤り | 未来についての予測を、現実とは乖離したものにしてしまう認知の歪み 例)未来のことを考えると、必ず何か悪いことが起こると予測してしまう |

ら行の心理用語
| 来談者中心療法 | カール・ロジャースは、指示的介入や従来の指導的・分析的なアプローチとは異なり、来談者(クライアント)が自己の問題を理解し、解決する能力を持っているとするものです。セラピストは、来談者の内的な成長を支援するために、共感的理解、無条件の肯定的関心、そして自己一致を提供します。 |
| ライフサイクル(SL)理論 | 消費者行動やマーケティングに関連する経済学的理論の一つです。この理論は、人々の消費行動が人生の異なる段階やライフステージに応じて変化することを説明しています。 |
| ライフストラクチャー理論 | ダニエル・レヴィンソンの理論は、成人の人生におけるライフコースの段階的な変化をモデル化し、個人の発達と変化に関する理解を提供し、人生のさまざまな時期における課題や転機に焦点を当て、成人の発達プロセスを論じました。 |
| ラケット感情 | 本来の感情を偽って無意識的に代用する偽物の感情である。この多くは子供のころに親や教育との関係から形成される。相手からのストローク(反応)を得る目的は達成するが、求めるストロークは返ってこないため満足はしない交流となる |
| ラベリング(レッテル貼り) | 人や特定の事象に対してたいした意味や根拠もないのに否定的に判断し、極端なラベル(レッテル)を張って相手を動かし影響を及ぼす。そのラベリングから浮かぶイメージに振り回されて、冷静な判断ができなくなってしまう |
| ラポール | 人々がお互いに信頼し、協力しやすい関係を築くためのコミュニケーションや相互作用の質を指します。相手との共感や理解がラポールの構築に重要です。 |
| ランチョンテクニック | このテクニックは、相手とランチや食事を共にすることを通じて、リラックスした雰囲気でコミュニケーションを取ることで、相手に好意を持たせたり、協力を促進することです。 |
| 理想化された親のイマーゴ | 親が自分の願望を満たしてくれると同時に、自分を支配しているような万能の神のような存在。幼い子供は現実の親をモデルにして、心の中の理想像であるイマーゴを育む |
| リバウンド効果 | 変化が持続的でない場合に現れる現象であり、人々の行動や状態が一時的に逆方向に戻ることを指します。 |
| リフレーミング | マイナスの感情や視点からポジティブなものに切り替えるだけでなく、逆にポジティブな状況をよりリアルな視点で見ることも含まれます。 |
| リンゲルマン効果 | 集団での作業において、個々のメンバーの努力が低下する現象を指します。 |
| 類型論と特性論 | 類型論は、人々を幾つかのカテゴリやタイプに分類し、それぞれのグループに共通する特性を考察するアプローチです。一方、特性論は、人々の個々の特性や性格要因を重視して研究するアプローチです。 |
| 裏面的交流 | 発信者と受信者の言葉と非言語のメッセージが不一致で、言葉の背景にある感情の本音を隠した交流であるり、鋭角や二重裏面交流などがある 言葉の裏側に別の意図があったり、感情を隠して演じるような交流で非言語な部分に現れる |
| レスポンデント条件付け | パブロフの犬の実験から始まった心理学の基本的な概念です。刺激と反応の関連付けを通じて新しい反応を獲得させるプロセスを指します。例えば、ベルを鳴らすことでエサが出るという結びつきができることを示しています。 |
| レストルフ効果 | 他の項目と異なる特徴を持つものが、記憶に残りやすくなる現象を指します。 |
| 劣等コンプレックス | 自己肯定感の不足や確信を持てないなど劣っていると強く認識していているが認めていない状態であり、自尊心を回復させる補償行動も多くなる |
| レッテル効果 | 特定のラベルやカテゴリーに分類されたものに対して、そのラベルに関連付けられた特性や属性を持つと認識する傾向を指します。 |
| レディネス | 学習や変化が達成されるための適切な時期や条件を指します。個人が新しい情報やスキルを取り入れる準備が整っていることを意味します。 |
| リトル・アルバート実験 | ジョン・ワトソンは「リトル・アルバート」という幼児を対象にした実験を行いました。この実験では、幼児の恐怖反応を条件づけることで、感情的な反応が学習によって形成されることを示しました。 |
| リレーショナルフレーム理論 | スティーブン・ヘイズの関係フレーム理論は、言語や思考の役割を強調しながら、人間の行動や認知のメカニズムを理解するための枠組みです。ACTでは、関係フレーム理論を活用して、言語や思考が個人の苦悩や制約をどのように形成し、変容させるかを理解し、柔軟な対応を促すアプローチを展開します。 |
| ロー・ボール・テクニック | 最初に魅力的な提案を行い、相手が受け入れる意思を示した後に、条件を変更してより不利な条件を提示するという方法が取られます。 |
| ロミオとジュリエット効果 | 外部からの干渉や反対があると、恋愛関係がかえって強化される現象を指します。 |
| ロリータコンプレックス | 男性が幼女や少女への性的興味や恋愛感情を抱いてしまう ・0〜5歳:ペドフェリア ・5〜10歳:ハイジコンプレックス ・10~13歳:アリスコンプレックス ・14〜18歳:ロリータコンプレックス |
| ロールシャッハ・テスト | 10枚のインクブロットカードを用いて被験者の反応を分析する投影法です。被験者が各カードに対して何を見ているかを説明することで、その人の認知プロセスや情緒的状態、性格特性を明らかにしようとするものです。 |
メンタルケア研究室


無料の3時間対面メンタルケアは、心理カウンセリングや精神療法、マインドフルネス、ストレス解消の同行な…
対面3時間無料メンタルケアでは、心理カウンセリング、心理療法の解説、症状の評価、心理教育、マインドフルネス、暴露療法、精神付添人によるストレス発散と心の安らぎを…

