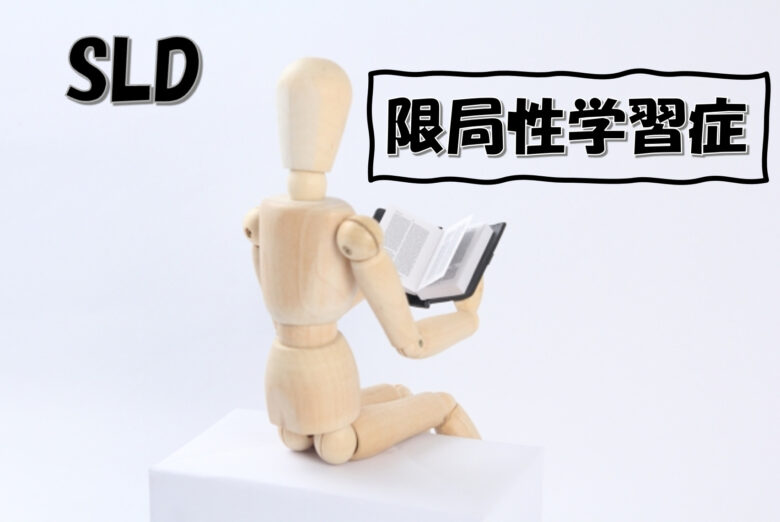読み書き、計算のいずれかに苦手な特性を感じていたら、神経発達症群の限局学習症かもしれません。
限局性学習症(SLD)の概念
知的発達症のように知的発達の遅れや聴覚、視覚に問題があるのではなくとも、読む、書く、計算のいずれかに関して極端に苦手な特異的な神経発達症群の発達障害です。教育の領域ではより広く学習障害と呼ばれますが、医学的には「読み書きの特異的な障害」または「計算能力など算数技能の獲得における特異的な発達障害」と呼ばれます。DSM-5の限局性学習症の定義では「読み」「書き」「計算」に限定され次のように示されています。
- 読字の障害
読字理解、速度または流暢性、正確性における特定の問題で、文字の並びが歪んで見えるや文字自体が二重に見えるなど状態は多様です。 - 漢字表出の障害
綴字の正確性、文法と句読点の正確さ、文章作成・構成における特定の問題で、特殊音節の拗音・促音・長音・撥音を書き間違うことがあります。「わ」と「は」のような同音の表記や「っ」「ょ」の小さい文字の認識が難しい、「め」と「ぬ」と「あ」、「わ」と「ね」など似た形の誤りが多く、各数の多い漢字では一部が異なることがあります。 - 算数の障害
計算の正確性、数字的記憶、記号の模写、それらの理解における特定の問題で、簡単な「5」+「3」などでも指を使うことや、時計の分針と時針の混同や九九算が苦手というケースがあります。
「読み」が苦手だと「書き」にも影響し「読み書き」の両方が苦手な「発達性ディスレクシア」と呼ばれます。また、学習症(LD)の範囲だとその他にも「話す」「聞く」「推論」「英語の読み書き」が苦手な症状を持つ人もいます。
学習症の発見は3歳児健診では困難であり、5歳児健診でも障害を発見する健診項目が十分ではありません。また、就学前後でも文字に興味を示さないような個人差や環境要因によって学習が遅れていただけというケースもあります。
原因は解明されていませんが、遺伝的に関連する遺伝子の変異や脳の発達において異常があることが報告されているほか、母親の早産や低出生体重児はハイリスクとなり、妊娠時のストレス、栄養不良、薬物使用などの環境要因が影響されることも指摘されています。特に両親のいずれかが発達性読み書き障害の家系では子供に65%に遺伝しています。
e-ヘルスネットでは2012年の小中学校教師を対象にした全国調査では4.5%存在するとしていて、ひらがなの学習障害は0.8〜2.1%の有病率としています。「特集・限局性学習症:稲垣真澄・米田れい子/総論:医療の立場から」では、発達性読み書き障害の有病率は0.7〜2.2%の間にあり、男児が1.5〜3倍女児より多いとしています。また、発達性読み書き障害の30%はADHDとASDと重複することが言われています。
算数障害の有病率は3〜6%とされていて男女比率はほとんど変わりませんが、イギリスでは算数障害の6割に発達性読み書き障害の合併が認められています。
このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。
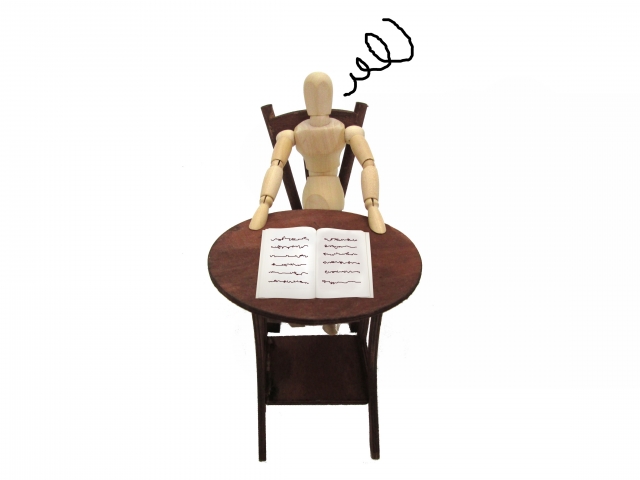
ICD-11による限局性学習症(SLD)の診断基準
限局性学習障害(SLD)は、ICD-11による診断基準では、次のように定義されています。
- 学習の遅れや困難がある
- 年齢に対して遅れた学習がある。
- 言語や読み書き、数学などの学習に困難がある。
- 学習に必要なスキル(言語、読解、計算など)の習得に問題がある。
- 知能は正常範囲内
- 知能指数(IQ)が正常範囲内(70以上)である。
- 知的障害、自閉スペクトラム症、精神疾患などの診断がつかない。
- 社会的・行動的問題がある
- 学校や社会生活で問題を抱える。
- 行動の制御や注意の持続、感情の調節などに問題がある。
- ソーシャルスキルの欠如や不器用さがある。
これらの3つの基準がすべて該当する場合に、限局性学習障害(SLD)と診断されます。ただし、診断は専門家による詳細な検査と判断が必要であり、個人によって症状の出方や重症度には差があります。
大人のSLD
限局性学習症(Specific Learning Disorder:SLD)は、読み・書き・計算などの学習面に特定の困難がある神経発達症群の一つです。発達障害の一種であり、幼少期に発現し、その特性は成人期まで持続することが多いです。ここでは、大人のSLDの概念や特徴について詳しく解説します。
- 大人のSLDの概念
-
- 発達期に始まる障害の持続
- SLDは子どもの頃に明確な診断がつかないまま成人に至ることが多く、「勉強が苦手な人」「不器用な人」などと誤認されやすいです。
- 成人になっても、学習面の困難さが仕事や日常生活で支障をきたすことがあり、二次障害(不安、抑うつ、自尊心の低下)につながることもあります。
- 診断されにくい背景
- 社会に出てからは、学業評価のような「学力を数値化する場面」が減るため、周囲が気づきにくく、自身も気づかないまま生きているケースが多いです。
- 一方で、職場での資料作成や報告書、計算業務などで困難を感じ、「何かがおかしい」と感じて受診する人もいます。
- 発達期に始まる障害の持続
- 大人に多いSLDの特徴
-
SLDには主に「読字障害(ディスレクシア)」「書字表出障害(ディスグラフィア)」「算数障害(ディスカリキュリア)」の3タイプがありますが、それぞれ大人になると以下のような特徴が見られます。
読字障害(ディスレクシア)
- 読むのが極端に遅い、または読み間違いが多い。
- 漢字を覚えられない/似た字を混同しやすい。
- マニュアルや長文資料を読むのに著しい苦手意識がある。
- 読むことに強いストレスを感じ、避ける傾向がある。
書字表出障害(ディスグラフィア)
- 文章を書くのに時間がかかる、構成がめちゃくちゃになりやすい。
- 漢字が思い出せない/ひらがなとカタカナを混同する。
- メモをとるのが非常に苦手。
- 誤字脱字が多く、修正しにくい。
算数障害(ディスカリキュリア)
- 簡単な暗算や計算が苦手、ミスが頻発。
- 時計の読みや金銭の計算に時間がかかる。
- 数字の桁や順序を混同しやすい(例:3桁の数字の転倒など)。
- グラフや統計を理解するのが難しい。
- 大人のSLDに関連する二次的な影響
-
- 自信喪失や自己評価の低下
- うつや不安症との併発
- 回避傾向(難しい仕事・勉強への抵抗)
- 職場での評価や人間関係の問題
- 支援と対応の例
-
- 認知特性をふまえた仕事の割り振り
- 読み上げソフト、音声入力、計算補助ツールなどの活用
- 課題の優先順位を明確にする支援
- 書字・読字に時間的配慮を設ける
大人のSLDの症例
個人が特定されないよう配慮した架空症例です。
「読み書きの特異的な障害」を持つ成人男性の症例
Aさん(35歳・男性)は中堅の製造業に勤める技術職の社員である。職務内容は現場での機械調整や点検作業が中心だが、近年は業務報告書や手順書の作成、メール対応といった書類業務の比重が増してきた。Aさんは仕事自体には誠実に取り組み評価も高いが、「文書を書くと何を言いたいのか分からない」「誤字脱字が多くて読みづらい」と上司から繰り返し指摘され、自信を失っていた。
子どもの頃から読書が極端に苦手で、教科書を音読する場面では他の子より著しく遅く、漢字もなかなか覚えられなかったが、「怠けている」「もっと努力すべき」と叱責され、本人も「自分はバカなんだ」と思い込むようになった。大学受験では英語や国語の読解問題に苦戦し、何度か浪人した末、理系の専門学校に進学。就職後は、計算や実技的な作業に強みを発揮し順調にキャリアを積んできた。
30代に入り、文書作成業務のストレスで体調を崩したことをきっかけに、心理相談を受けた。その中でWAIS-IVおよび読字・書字に関する検査が実施され、「特異的読字障害および書字障害(ディスレクシア・ディスグラフィア)」の可能性が示唆された。Aさんは「怠けではなかったことにほっとした」と語り、上司には検査結果を開示。職場では書類作成時に音声入力ソフトを使うことや、読み上げアプリで資料に対応するなど、合理的配慮が導入された。現在は自己理解を深めながら、業務への適応を図っている。
SLDの「算数障害」を持つ成人男性の症例
Bさん(28歳・男性)は、接客業から事務職に転職した会社員である。職場では売上入力や在庫管理、請求書作成など数字を扱う業務が増え、ミスが頻発していた。特に桁の見間違いや数字の転記ミス、簡単な計算ミスが多く、同僚から「不注意」「確認不足」と指摘されることが続いた。本人も何度も確認しているつもりだったが、同じようなミスを繰り返し、強い自己否定感を抱くようになっていた。
振り返れば、学生時代から数学には極端な苦手意識があった。九九の暗記に時間がかかり、時計の読み方や文章題もなかなか理解できず、定期テストでは毎回赤点ギリギリ。にもかかわらず国語や社会科目では平均以上の成績を出していたため、周囲には「やればできるのに怠けている」と誤解されていた。大学では文系学部に進学し、数学を避けることで何とか卒業した。
転職後、業務上の困難から心身の不調が出始めたため、産業医の勧めで心理士のカウンセリングを受ける。WAIS-IVの結果では、言語理解や処理速度は平均以上だったが、ワーキングメモリおよび数的推理に著しい弱さが見られた。加えて、算数技能に特化した検査で、数の概念や数量比較、筆算などの基礎的なスキルに困難があることが明らかになり、「限局性学習症(算数障害)」の診断に至った。
本人は「ずっと自分だけがなぜできないのか分からなかった」と安堵し、上司とも相談の上、業務を見直すことになった。現在は、複雑な計算業務は他の職員と分担し、計算ソフトやチェックリストを活用することでエラーを減らしている。Bさんは今、自分の特性を理解しながら、安定して仕事を続けている。
大人のSLDを自己でできる治療・セルフサポート法
大人のSLD(限局性学習症)における治療やサポートは、根本的に「脳機能の特性による情報処理の苦手さ」を前提に、困りごとを軽減することを目的とします。
無理に「苦手を克服しよう」とするより、「どう補うか・避けるか・工夫するか」を主体的に考えることが、成人SLDにおいては最も現実的で有効なセルフサポートです。
- 読み・書き・計算の中で「何が」「どんなときに」難しいかを具体化する。
- 苦手の原因が「注意力」や「記憶力」ではなく、「情報処理の方式」によることを理解する。
- WAIS-IVや学習機能検査(読み書き検査、数処理検査など)を受けることで、自分の認知プロファイルを知ることも有効。
- 読み上げソフトの利用(例:Voice Dream Reader、Google ドキュメントの読み上げ機能)
- 音声入力・変換ツール(例:Google音声入力、スマホの音声メモ)
- 文の構造を視覚化する(箇条書き、マインドマップ、フローチャート)
- 書く作業を分業・省略(例:ひとりで書かず、口述や共同編集を使う)
- 文法・誤字チェックソフトを使う(例:Grammarly、日本語校正くん)
- 計算機アプリの常用・桁チェック機能を活用
- テンプレートやフォームを使ってミスを予防
- 数値を文字や色で視覚化(例:重要な数字を太字にする、色分けする)
- 金銭・時間など「量」の感覚を数直線や図表で補助
- 数字の読み上げツール・読み上げ音声で確認
- 「できない=ダメ」ではないと自分に言い聞かせる
→ 苦手を「工夫でカバーすべき分野」と再定義する。 - 小さな成功を可視化する
→ タスクを細かくし、達成したことを見える化。 - セルフ・コンパッションを養う
→ 自分の困難にやさしく寄り添い、過剰な自己批判を避ける。
- 職場や家庭に特性を共有する(信頼できる相手に)
- 業務や家事の分担を調整する(自分の得意不得意を活かす)
- 合理的配慮を求める準備をしておく(必要なら診断書や検査結果を活用)
- 発達障害支援センター、精神科医などによる認知検査やカウンセリング
- 就労支援機関(例:就労移行支援、発達障害者就労支援センター)も情報源に
大人のSLDの職場での工夫
学習症がある方が仕事をする上での対処方法は、まず自分の症状と苦手な特性を職場や同僚に理解してもらうよう相談するところから始まります。
苦手を「ミスを防ぐための戦略」で補い、得意な部分にエネルギーを集中できるようにすることが、成人SLDにおける働き方のカギです。
SLDやLDで生きづらさが原因となり、社交不安障害やトラウマ、うつ病などの二次障害を感じた際には精神科や心療内科、心理カウンセリングを受けることをお奨めします。
- 会議などにはボイスレコーダを使用して、繰り返し聞く。
- マニュアルなどの説明は口頭を含めて説明してもらう。
- 作業などは動画を使用して理解する。
- スマホやタブレットなどの使用を許可してもらう。
読み上げソフトや計算アプリの使用や書くことは入力するなどできる環境づくり - 就職はハローワークや障害者就業支援などの機関を利用する。
- マルチモーダルに情報を提示
→ 文字+図解、音声+動画など、複数の形式で情報を得られるようにする。 - 業務手順をマニュアル化・フローチャート化
→ 書き出すことで記憶に頼らず対応できる。 - 「困っていることは伝えてよい」職場文化をつくる
→ 特性を開示しやすくなることで孤立感や不安を軽減。 - リマインダー・チェックリストの活用
→ ToDoリスト、タスク管理アプリ(Trello、Notionなど)を活用。
- 読み上げソフトや機能を使う(例:PCの読み上げ機能、Voice Dream Reader)
- 長文資料は要約をもらう/先に箇条書きで概要を提示
- フォント・レイアウトを工夫する
→ ゴシック体、行間を広めに、1行あたりの文字数を減らす - 文章を画像・表・図などに変換してもらう
→ 特にマニュアル系文書は視覚的提示が有効
- 音声入力を使って書く(例:Google音声入力、スマホの音声メモ)
- テンプレートを用意して記述の負担を軽減
- メール文などは定型文を登録しておく(Gmailの定型返信など)
- 誤字脱字の確認はソフトに任せる(例:Grammarly、日本語校正くん)
- Excelや電卓など数値処理を機械化する(数式を組んで自動計算)
- 数字のチェックは「読む」「言う」「見せる」の三重確認
- 帳票や報告書はテンプレート化し、確認手順を明文化
- グラフ・表などは視覚化された形式で確認する
- 金額や在庫数などのミスは、他者と「ダブルチェック」で担保
- 口頭説明をメモだけでなく録音することを許可してもらう
- 報告・連絡・相談は箇条書きや図解を使うと明確になりやすい
- 苦手分野は同僚にサポートを依頼し、得意な部分で補う関係を築く
- 書類作成の時間的余裕
- 読み書きの代替手段(例:口頭報告、音声入力)
- 不得意な業務の一部変更や分担
- 指示の出し方を明確にする(口頭+書面、マニュアル整備など)
限局性学習障害の治療法
- 認知行動療法
認知行動療法は、問題行動や思考パターンを変えることで、障害を克服することを目的とした治療法です。患者は、自分自身の思考と行動を自己評価し、問題の特定と解決方法を見つけることを促されます。 - 認知リハビリテーション
認知リハビリテーションは、認知的機能の改善を目的とした治療法で認知トレーニング、記憶トレーニング、注意力トレーニング、問題解決トレーニングなどが含まれます。 - 構造化された環境
構造化された環境は、患者が正しい方法でタスクを完了できるようにすることで、学習の障害を緩和することを目的としています。例えば、カレンダーや時計を使ってスケジュールを管理したり、チェックリストを使用したり、タスクを小さなステップに分割することで、患者がタスクを完了しやすくなります。
治療法は、患者の症状や状況に応じてカスタマイズされます。個別に合わせた治療を受けることで、症状の改善が期待されます。また、家族や学校、職場などの環境を改善することも重要です。専門家の指導の下、適切な治療を受けることが重要です。
読み書き・計算の特異的な障害セルフチェック(成人向け)
限局性学習障害(SLD)の「読み」「書き」「計算」の自己評価を目的とした50問のセルフチェックリストです。各質問に対して「はい」「いいえ」で回答してください。ただし、このチェックリストは自己評価のためのものであり、正式な診断を行うためには専門家の評価が必要です。また、「読み」「書き」「計算」それぞれに限定したセルフチェックリストもご利用ください。
| № | 限局性学習障害の自己評価セルフチェックリスト |
|---|---|
| 1. | 読むことが非常に困難だと感じることが多いですか? |
| 2. | 書くことに時間がかかり、ミスが多いと感じますか? |
| 3. | 数学の基本的な計算に苦労しますか? |
| 4. | 新しい単語を覚えるのが難しいですか? |
| 5. | 語彙を適切に使うのに苦労しますか? |
| 6. | 読み間違いが頻繁にありますか? |
| 7. | 書いた文章の意味が自分でも分からなくなることがありますか? |
| 8. | 数字の順番を間違えることが多いですか? |
| 9. | 計算問題で数の概念が理解できないことがありますか? |
| 10. | 読んだ文章の内容を理解するのに時間がかかりますか? |
| 11. | 文章を書くときに文法ミスが多いと感じますか? |
| 12. | 掛け算や割り算の基本的な原理を理解するのに苦労しますか? |
| 13. | 読み進めるスピードが遅いと感じますか? |
| 14. | 書くときに単語のつづりを間違えることが多いですか? |
| 15. | 計算問題で位取りを間違えることが多いですか? |
| 16. | 読んだ内容を記憶するのが難しいですか? |
| 17. | 書いた文章の構成が乱れることが多いですか? |
| 18. | 数字を逆さに書いてしまうことが多いですか? |
| 19. | 読んだ内容をすぐに忘れてしまうことがありますか? |
| 20. | 文章を書くときに適切な句読点を使うのが難しいですか? |
| 21. | 数学の文章問題を理解するのが難しいですか? |
| 22. | 音読するのが苦手ですか? |
| 23. | 読んだ内容を他人に説明するのが難しいですか? |
| 24. | 数字の順序を覚えるのが苦手ですか? |
| 25. | 音読するときに言葉が詰まることが多いですか? |
| 26. | 読んだ内容を自分の言葉で要約するのが難しいですか? |
| 27. | 数字を見てすぐに理解できないことがありますか? |
| 28. | 語彙が貧弱だと感じることが多いですか? |
| 29. | 書くときに文字の形が崩れることが多いですか? |
| 30. | 数字を暗記するのが難しいですか? |
| 31. | 読むときに行を飛ばしてしまうことがありますか? |
| 32. | 文章を書くときに適切な表現を選ぶのが難しいですか? |
| 33. | 計算問題で概念の理解に苦しむことが多いですか? |
| 34. | 読むことが苦痛に感じることが多いですか? |
| 35. | 書くときに単語を繰り返し間違えることが多いですか? |
| 36. | 数字の大小関係を理解するのが難しいですか? |
| 37. | 読んだ内容を理解するのに時間がかかりますか? |
| 38. | 書くときに文字を逆さに書いてしまうことがありますか? |
| 39. | 数字を使った問題解決が難しいと感じますか? |
| 40. | 読むときに意味が分からない単語が多いと感じますか? |
| 41. | 書くときに文の構造が混乱することが多いですか? |
| 42. | 数字を操作するのが難しいと感じますか? |
| 43. | 読むときに集中力が続かないことが多いですか? |
| 44. | 書いた文章の内容が論理的でないと感じることが多いですか? |
| 45. | 数字のパターンを理解するのが難しいと感じますか? |
| 46. | 読んだ内容を他人に正確に伝えるのが難しいですか? |
| 47. | 書くときに時間がかかりすぎると感じますか? |
| 48. | 数字を使った作業でストレスを感じることが多いですか? |
| 49. | 読むことがストレスになることがありますか? |
| 50. | 書くことがストレスになることがありますか? |
評価
各質問に対して「はい」と答えた数を集計します。
| 合計点 | 評価内容 |
|---|---|
| 0~10点 | 特に問題は見られない可能性が高いです。 |
| 11~20点 | 多少の困難があるかもしれませんが、日常生活に大きな支障はないでしょう。 |
| 21~30点 | 限局性学習障害の可能性があるため、専門家の助けを求めることをお勧めします。 |
| 31~40点 | 限局性学習障害の可能性が高く、専門的な評価と支援が必要です。 |
| 41~50点 | 限局性学習障害の可能性が非常に高いため、すぐに専門家に相談してください。 |
限局性学習症(読み)セルフチェックリスト
このセルフチェックリストは、成人の限局性学習症(読み)を評価するためのものです。各質問に対して「はい」または「いいえ」で回答してください。ただし、このチェックリストは自己評価のためのものであり、正式な診断を行うためには専門家の評価が必要です。
| № | 限局性学習症(読み)自己評価セルフチェックリスト |
|---|---|
| 1. | 読む速度が非常に遅いと感じますか? |
| 2. | 読んだ内容を理解するのに時間がかかりますか? |
| 3. | 読んでいるときに行を飛ばしてしまうことがありますか? |
| 4. | 読んだ内容をすぐに忘れてしまうことがありますか? |
| 5. | 読むときに意味が分からない単語が多いと感じますか? |
| 6. | 文章の内容を一度読んだだけでは理解できないことがありますか? |
| 7. | 読むことが苦痛に感じることが多いですか? |
| 8. | 読んだ内容を他人に説明するのが難しいですか? |
| 9. | 読んでいるときに言葉が詰まることが多いですか? |
| 10. | 読んだ内容を自分の言葉で要約するのが難しいですか? |
| 11. | 読んでいるときに集中力が続かないことが多いですか? |
| 12. | 読んだ内容を記憶するのが難しいですか? |
| 13. | 読み間違いが頻繁にありますか? |
| 14. | 語彙が貧弱だと感じることが多いですか? |
| 15. | 読んだ文章の意味が自分でも分からなくなることがありますか? |
| 16. | 読むときに適切な句読点を使うのが難しいですか? |
| 17. | 読んだ内容を理解するのに時間がかかりますか? |
| 18. | 読むことがストレスになることがありますか? |
| 19. | 読むことに集中するのが難しいと感じますか? |
| 20. | 読んだ内容をすぐに忘れてしまうことがありますか? |
| 21. | 読むことが非常に困難だと感じることが多いですか? |
| 22. | 読んだ内容を覚えるのが難しいですか? |
| 23. | 読んだ内容を正確に伝えるのが難しいですか? |
| 24. | 読むときに言葉が詰まることが多いですか? |
| 25. | 読むときに行を飛ばしてしまうことがありますか? |
| 26. | 読むことが苦手だと感じることが多いですか? |
| 27. | 読む速度が遅いと感じることが多いですか? |
| 28. | 読むことが苦痛に感じることが多いですか? |
| 29. | 読むことがストレスになることがありますか? |
| 30. | 読んだ内容を理解するのに苦労することが多いですか? |
限局性学習症(読み)自己評価セルフチェックリスト
評価
各質問に対して「はい」と答えた数を集計します。
| 合計点 | 評価内容 |
|---|---|
| 0~5点 | 特に問題は見られない可能性が高いです。 |
| 6~10点 | 多少の困難があるかもしれませんが、日常生活に大きな支障はないでしょう。 |
| 11~15点 | 限局性学習症(読み)の可能性があるため、専門家の助けを求めることをお勧めします。 |
| 16~20点 | 限局性学習症(読み)の可能性が高く、専門的な評価と支援が必要です。 |
| 21~30点 | 限局性学習症(読み)の可能性が非常に高いため、すぐに専門家に相談してください。 |
限局性学習症(書き)自己評価セルフチェックリスト
このセルフチェックリストは、成人の限局性学習症(書き)を評価するためのものです。各質問に対して「はい」または「いいえ」で回答してください。ただし、このチェックリストは自己評価のためのものであり、正式な診断を行うためには専門家の評価が必要です。
| № | 限局性学習症(書き)自己評価セルフチェックリスト |
|---|---|
| 1. | 書くときに適切な単語が思い浮かばないことがありますか? |
| 2. | 文法ミスが頻繁に起こりますか? |
| 3. | 文章を書くときに適切な句読点を使うのが難しいですか? |
| 4. | 書いた文章の意味が自分でも分からなくなることがありますか? |
| 5. | 文章を書くのに時間がかかりすぎると感じますか? |
| 6. | 単語のつづりを間違えることが多いですか? |
| 7. | 書いた文章の構成が乱れることが多いですか? |
| 8. | 書くときに文字の形が崩れることが多いですか? |
| 9. | 書くことが非常に困難だと感じることが多いですか? |
| 10. | 文章を書くときに適切な表現を選ぶのが難しいですか? |
| 11. | 書いた内容を一度見直さないと理解できないことがありますか? |
| 12. | 書くことがストレスになることがありますか? |
| 13. | 書くときに同じミスを繰り返すことが多いですか? |
| 14. | 書いた文章が論理的でないと感じることが多いですか? |
| 15. | 書いた内容が他人に理解されにくいと感じますか? |
| 16. | 文章を書くときにアイデアが浮かばないことがありますか? |
| 17. | 書いた文章を修正するのが難しいと感じますか? |
| 18. | 書くことに集中するのが難しいですか? |
| 19. | 書いた文章が長すぎたり短すぎたりすることが多いですか? |
| 20. | 文章を書くのが嫌いだと感じることが多いですか? |
| 21. | 書くときに手が疲れることがありますか? |
| 22. | 書いた文章が自分の意図と異なることが多いですか? |
| 23. | 文章を書くときに順序を間違えることが多いですか? |
| 24. | 書くことが苦手だと感じることが多いですか? |
| 25. | 文章を書くのにプレッシャーを感じることが多いですか? |
| 26. | 書くときに適切な単語が思い浮かばないことがありますか? |
| 27. | 文章を書くのに時間がかかりすぎると感じますか? |
| 28. | 書いた文章の意味が自分でも分からなくなることがありますか? |
| 29. | 書くことが苦痛に感じることが多いですか? |
| 30. | 書いた内容を他人に説明するのが難しいですか? |
限局性学習症(書き)自己評価セルフチェックリスト
評価
各質問に対して「はい」と答えた数を集計します。
| 合計点 | 評価内容 |
|---|---|
| 0~5点 | 特に問題は見られない可能性が高いです。 |
| 6~10点 | 多少の困難があるかもしれませんが、日常生活に大きな支障はないでしょう。 |
| 11~15点 | 限局性学習症(書き)の可能性があるため、専門家の助けを求めることをお勧めします。 |
| 16~20点 | 限局性学習症(書き)の可能性が高く、専門的な評価と支援が必要です。 |
| 21~30点 | 限局性学習症(書き)の可能性が非常に高いため、すぐに専門家に相談してください。 |
限局性学習症(計算)セルフチェックリスト
このセルフチェックリストは、成人の限局性学習症(計算)を評価するためのものです。各質問に対して「はい」または「いいえ」で回答してください。ただし、このチェックリストは自己評価のためのものであり、正式な診断を行うためには専門家の評価が必要です。
| № | 限局性学習症(計算)自己評価セルフチェックリスト |
|---|---|
| 1. | 基本的な計算に時間がかかりますか? |
| 2. | 計算問題を解くときに数字を間違えることが多いですか? |
| 3. | 掛け算や割り算の基本的な原理を理解するのに苦労しますか? |
| 4. | 数字の順序を間違えることが多いですか? |
| 5. | 計算のステップを忘れてしまうことがありますか? |
| 6. | 数字を逆さに書いてしまうことが多いですか? |
| 7. | 数学の文章問題を理解するのが難しいですか? |
| 8. | 数字を覚えるのが難しいと感じますか? |
| 9. | 数学の問題を解くのが苦痛に感じることが多いですか? |
| 10. | 計算を行うときに手が疲れることがありますか? |
| 11. | 数字の大きさを比較するのが難しいと感じますか? |
| 12. | 計算を行うときに集中力が続かないことが多いですか? |
| 13. | 数字のパターンを理解するのが難しいと感じますか? |
| 14. | 基本的な数学の概念を理解するのに苦労しますか? |
| 15. | 計算問題を解くのに他人の助けが必要だと感じますか? |
| 16. | 数字を操作するのが難しいと感じますか? |
| 17. | 計算問題で位取りを間違えることが多いですか? |
| 18. | 計算結果をチェックするのが苦手ですか? |
| 19. | 数字を使った作業でストレスを感じることが多いですか? |
| 20. | 数学の授業や講義についていくのが難しいと感じますか? |
| 21. | 数字を覚えるのが苦手だと感じることが多いですか? |
| 22. | 計算問題を解くときに手順を間違えることが多いですか? |
| 23. | 数字を見てすぐに理解できないことがありますか? |
| 24. | 計算を行うときにミスが頻繁に起こりますか? |
| 25. | 数学のテストで良い成績を取るのが難しいと感じますか? |
| 26. | 計算問題を解くのが嫌いだと感じることが多いですか? |
| 27. | 数字の概念を理解するのに時間がかかりますか? |
| 28. | 計算問題を解くのにプレッシャーを感じることが多いですか? |
| 29. | 数学の問題を解くときにイライラすることが多いですか? |
| 30. | 計算を行うときにストレスを感じることがありますか? |
限局性学習症(計算)自己評価セルフチェックリスト
評価
各質問に対して「はい」と答えた数を集計します。
| 合計点 | 評価内容 |
|---|---|
| 0~5点 | 特に問題は見られない可能性が高いです。 |
| 6~10点 | 多少の困難があるかもしれませんが、日常生活に大きな支障はないでしょう。 |
| 11~15点 | 限局性学習症(計算)の可能性があるため、専門家の助けを求めることをお勧めします。 |
| 16~20点 | 限局性学習症(計算)の可能性が高く、専門的な評価と支援が必要です。 |
| 21~30点 | 限局性学習症(計算)の可能性が非常に高いため、すぐに専門家に相談してください。 |
標準精神医学第8版:尾崎紀夫・三村將・水野雅文・村井俊哉/医学書院
成重竜一郎:多動性障害(注意欠如/多動性障害ADHD)・精神科治療学
金生由紀子、浅井逸郎:チックのための包括的行動介入セラピストガイド/丸善出版
次良丸睦子、五十嵐一枝:発達障害の臨床心理学/北大路書房
柴崎光世、橋本優花里:神経心理学/朝倉書店
村上宣寛:IQってなんだ・知能をめぐる神話と真実/日経BP社
DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 高橋三郎・大野裕監修/医学書院