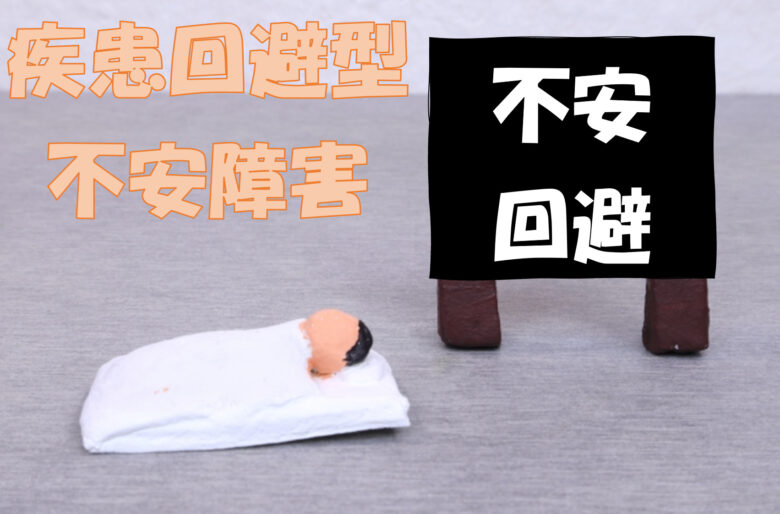病気不安症「IAD」の病名から疾患型不安障害へ変更した架空のケースから二つの症状の理解・知識と比較を学ぶ精神医学物語-6弾
病気不安症から疾患回避型不安障害への変更の症例物語
仮名、村上美穂は毎年健康診断を受けていた。彼女は自分の健康には非常に注意しており、健康的な食事と運動を欠かさず行っていた。しかし、ある年の健康診断の結果には異常が見つかり、心臓の数値が高くなっていた。これを受け、彼女は不安に陥った。医師に相談し、心臓に関する検査を受けることになった。その検査の結果、特に異常は見つからず、医師は彼女に「大丈夫ですよ! 緊張したり、運動不足だったりすると、心臓の数値が高くなることもありますから」と説明した。
しかし、美穂は繰り返し検査を受け、さらには自分自身でネットで調べるようになった。彼女は恐怖心にとらわれ、毎日自分自身を診断し、異常を見つけるたびに、再び病院へ通うようになった。また、自分が病気でないことを認めようとせず、自分が検査や治療を受けないと死んでしまうと思い込んでしまった。
その後も、彼女は体調不良を感じると必ず病院に行くようになり、仕事やプライベートの時間を削ることも多くなった。友人たちからも心配され、家族からも「病気じゃないんだから」と言われてはいたが、自分の不安をコントロールできなかった。
そんなある日、美穂は新しい心療内科の医師に出会った。その医師は、病気不安症という病気があることを教えてくれた。彼女は、自分が病気ではなく病気に対する恐怖を持っているだけだと知り、少し安心した。
新しい医師からは、認知行動療法と薬物療法の併用が勧められた。彼女は、自分が病気にかかってしまうことを恐れていたが、新しい医師からは、「自分に何か異常があるのではなく、誰にでも健康でいたいという気持ちがある」と教えられた。美穂は、自分自身を変えようと思い治療を開始した。
最初は、認知行動療法に抵抗があったが、徐々に自分の考え方が変わっていくのを感じた。過去には「健康診断で異常があると、すぐに病気だと思ってしまう」という思い込みがあったが、今では「異常値が出ても、健康的な生活を続けることで改善できる可能性がある」と考えるようになった。また、過剰な検査を受けることや病気について調べることも減らし、健康的な生活習慣を取り入れることに力を入れるようになった。
治療を受けてからしばらくして、美穂は病気不安症から疾患回避型不安障害に診断が変更された。医師の説明だと、この名称が採用されたのは、病態が病気や健康に対する異常な不安だけでなく、病気や健康に対する回避行動も特徴としていることを表現されているそうだ。彼女は納得できると思った。また、この名称は、従来の病気不安症よりもより中立的で、患者の健康への不安をより的確に表現しているようだ。
今では、美穂は以前よりも自分の健康に対する不安が軽減され、より健康的な生活を送っている。
このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。
病気不安症(IAD)の概要
病気不安症(illness anxiety disorderillness :IAD)とは、病気にかかることや病気を発症しているかもしれないという過度な不安・恐怖が主な症状となる精神障害です。別名、健康不安障害、ヒポコンドリアとも呼ばれます。
病気不安症は、自分が重い病気にかかっている、またはかかるのではないかと過剰に不安を抱く精神疾患です。医学的検査で異常がない、または軽微な症状しかない場合でも、不安が持続してしまいます。
この疾患の特徴は、体のあらゆる症状を自己診断して「自分は病気だ」と不安になってしまうことです。例えば、頭痛や胸痛、腹痛、めまい、息切れなどの症状が現れると、自分は脳腫瘍や心臓病、がんなど重大な病気にかかっているのではないかと不安になります。また、自分が病気であることを疑いつつも、病院で検査しても異常が見つからない場合でも、「何か見落とされている」という不安を抱えることがあります。
また、病気や健康に関連する情報を避けたり、健康に関するテレビ番組やニュースを見ないようにしたり、病院や医師の診察を受けることを避けたりするなど、病気や健康に関する行動を制限する傾向があります。
このような不安は、病気を引き起こすリスクを減らすための正常な注意と違い、病気がないにもかかわらず、日常生活や社会生活に支障をきたすほど強いものになることがあります。逆に病気であるにもかかわらず医療機関での診察や検査を受けることを避けたり、病気に関する情報を避けたりすることがあります。
IADの主な臨床症状は、次のようなものが挙げられます。
- 頻繁な身体検査や医療機関への受診の欲求
- 軽度な症状に対する過剰な不安や恐怖
- 異常なまでに健康に対するこだわり
- 自己診断や自己治療の傾向
- 病気に対する過剰な情報収集
- 仕事や社会生活への影響
- 避けるべき場所や物の拡大
- 病気や健康に対する回避行動
- 病気や健康に関連する情報を避ける
- 医療機関での診察や検査を受けることを避ける
- 不眠や食欲不振、身体的な症状の増悪などの身体的な問題
- 不安やパニック発作などの精神的な問題
主な特徴
| 特徴 | 内容 |
| 病気に対する強い恐怖 | 自分が深刻な病気にかかっていると強く思い込む |
| 医師の診断にも納得しない | 検査や診察で「異常なし」と言われても安心できない |
| 過度な健康チェックや病院通い | 繰り返し医師に相談、ネット検索、身体の感覚をチェックする |
| 逆に受診を避けることもある | 不安が強すぎて、病気と診断されるのが怖くなり病院を避ける場合もある |
| 日常生活に支障が出る | 不安のために仕事や人間関係、生活全体に悪影響が出る |
これらの症状が、日常生活や社会生活に支障をきたすほど強い場合、病気不安症の可能性が考えられます。しかし、これらの症状があるからといって、必ずしもIADであるとは限りません。過剰な不安や恐怖を感じる場合は、精神科医や心療内科医の受診を検討することが望ましいと判断してください。

病気不安症の診断基準
- 病気や病気に関する身体的な異常に対して、持続的な強い不安や恐怖を感じ、以下のような症状が6ヶ月以上続いている。
- 病気や健康に対する異常な不安により、日常生活に支障が出ている。
- 疾患の存在を過剰に懸念し、またはその可能性が極めて低い場合でも、疾患に関連する身体的な症状を強く注目する。
- 病気や健康に関する情報に過度に注意し、過剰に健康を維持するための行動(例えば、病気や健康に関する情報を避けたり、医療機関での診察や検査を避けたりするなど)を行っている。
- 病気や病気に関連する不安や恐怖によって、日常生活や社会的・職業的機能に支障がある。
- 他の心理疾患や医学的な疾患による理由ではなく、診断のための偽病的行動ではない。
上記の基準に合致する場合、病気不安症と診断されます。ただし、診断にあたっては、他の病気や疾患によって引き起こされる健康不安と区別する必要があります。また、健康に関する情報を収集すること自体は健康的であり、病気不安症の診断には、病気や健康に関する情報を過剰に避ける行動があるかどうかも考慮されます。
- 深刻な病気を患っている、あるいは患うことへの強い不安が6か月以上持続。
- 身体症状は軽度または存在しないが、不安は過剰。
- 健康に関する行動(例:体のチェック、医師の訪問)が過剰、あるいは回避行動(病院に行かないなど)が見られる。
- 他の精神疾患(たとえば全般性不安障害やうつ病など)では説明できない。
似ているが異なる疾患との違い
| 疾患名 | 主な違い |
| 心気症(旧分類) | DSM-5で病気不安症と身体症状症に再分類された |
| 身体症状症 | 実際に身体症状があり、それに対する過度な心配が中心 |
| 強迫症 | 強迫観念(例:「病気になるかもしれない」)と儀式的行動の組み合わせ |
| 全般性不安障害 | 健康だけでなく多方面への漠然とした不安が主 |
IADの経過・予後
病気不安症の経過は個人差が大きく、一過性のものから慢性的なものまであります。一部の患者は数ヶ月で自然に改善する場合もありますが、症状が持続する場合もあります。
また、挿話的、再発性、慢性的な側面があります。挿話的な場合は、特定の疾患に関する懸念がある期間に限定され、その期間が過ぎると自然に症状が改善することが多くなります。再発性の場合は、症状が一度改善した後に再発することがあります。慢性的な場合は、症状が長期にわたって持続することがあります。
寛解については、治療や自然治癒によって症状が改善する場合がありますが、病気不安症は再発する可能性があるため、注意が必要です。
高齢者においては、病気への不安が記憶の低下を招くことがあります。この場合、病気不安症そのものが原因となっている可能性もありますが、高齢者には認知機能の低下が伴う場合があるため、それらの要因も考慮する必要があります。
総じて言えることは、病気不安症の経過や予後は患者個人によって異なるため、専門医の適切な治療とフォローアップが必要であるということです。
IADの病因・病態
病気不安症の病因や病態については、まだ完全に解明されているわけではありませんが、いくつかの研究や仮説が存在しています。
病因としては、遺伝的、神経生物学的、心理社会的な要因が考えられています。遺伝的な要因としては、遺伝子の多型性が関与しているとする研究もあります。また、脳の生理学的な変化や脳内物質のバランスの変化も疾患病気不安症の病態に関与しているとされています。
心理社会的な要因としては、ストレスやトラウマ、過剰な健康情報の受容、病気に対する社会的なスティグマなどが関与しているとされています。
病気不安症の病態については、過剰な恐怖反応や認知バイアス、反復的な回避行動などが関与しているとされています。具体的には、健康に関する情報や症状に対する過剰な注意、誤った自己診断の傾向、回避行動が生じ、これらが不安症状を強化する悪循環が繰り返されることで、病気不安症が慢性化していくとされています。
病気不安症の疫学に関する研究はまだ限られていますが、次のような情報が報告されています。
病気不安症の背景・要因
- 幼少期の病気体験や家族の病気への過剰な反応
- ネット検索(いわゆる「サイバーコンドリア」)
- 不安傾向やうつ傾向の強い性格
- 親からの過保護や健康不安のモデリング
- 有病率
病気不安症の有病率は、様々な国や地域で調査が行われていますが、その中でもっとも高い有病率が報告されているのは日本で、一部の調査では、成人の総合有病率が5〜6%に達するとされています。一方で、他の国々ではより低い有病率が報告されています。 - 発症年齢
病気不安症は、多くの場合、青年期から中年期にかけて発症しますが、小児期や高齢期でも発症することがあります。 - 性差
女性の方が男性よりも発症しやすいとされていますが、1:1との報告もあります。 - 関連疾患
病気不安症は、他の不安障害やうつ病、身体症状症(身体表現性障害)、適応障害などとの合併が報告されています。
病気不安症は「症状がない」のに「強い苦しみ」があるため、周囲や医療者にも理解されにくく、孤立しやすい疾患です。正しい理解と、共感的かつ一貫した対応が非常に重要です。
ただし、病気不安症については、疫学調査がまだ不十分なため、これらの数字には限界があります。今後の調査によってより正確な情報が得られることが期待されています。
IADの治療
病気不安症の治療法には、認知行動療法や薬物療法があります。
認知行動療法では、現実的な思考や行動を身につけることで、病気への不安を軽減することができます。
具体的には、症状に対する理解や情報収集、症状に対する対処方法の学習、身体的な緊張を解消するリラクゼーション法などが行われます。対人療法では、信頼できる相手や家族、友人などとのコミュニケーションを増やし、支援を受けることで不安を軽減することが目的とされています。
また、回避行動を改善することもあります。まず、患者の不安を引き起こす思考パターンや信念を特定し、それらを払拭するための新しい思考パターンや信念を学習します。その上で、回避行動を徐々に行わないように訓練していきます。 例えば、患者が病気にかかることを恐れている場合、医療機関への受診や健康診断などについて、少しずつでも行動を変えていくように指導されます。
薬物療法では、抗うつ薬や抗不安薬が使用されることがあります。特に、過度の不安がある場合は、抗不安薬が使用されることがあります。また、うつ病との合併が見られる場合には、抗うつ薬が併用されることもあります。
■ 治療法
- 認知行動療法(CBT)
→ 思考の歪み(例:「小さな痛み=がんかもしれない」)に気づき、修正する。 - 薬物療法
→ 抗うつ薬(SSRIなど)が使われることがある。 - 心理教育・共感的対応
→ 患者の不安を否定せず、丁寧に説明・サポートする関わりが重要。
治療法は個人によって異なります。治療計画は、医師や心理療法士との相談に基づいて決定されます。適切な治療法を見つけ、専門家の指導を受けることが重要です。
病気不安症のセルフチェックリスト
病気不安症(Illness Anxiety Disorder, IAD)の自己評価のためのセルフチェックリストは、健康に関する不安や行動を評価するのに役立ちます。次に35問のセルフチェックリストを示します。各質問に対して、各質問に対して、「はい」か「いいえ」で回答してください。
| № | 病気不安症のセルフチェックリスト35問 |
|---|---|
| 1. | 自分の健康について常に心配している。 |
| 2. | 少しの体調の変化でも深刻な病気かもしれないと不安になる。 |
| 3. | インターネットで症状を調べることが多い。 |
| 4. | 医師の診断に納得できず、複数の医師に相談することがある。 |
| 5. | 健康に関する情報を頻繁に検索する。 |
| 6. | 病気についてのニュースや記事を読むと不安になる。 |
| 7. | 健康診断の結果が心配で、再検査を希望することが多い。 |
| 8. | 症状がなくても、定期的に病院に行くことがある。 |
| 9. | 家族や友人に自分の健康について何度も話す。 |
| 10. | 病気の可能性を常に考えてしまう。 |
| 11. | 医師の診断に対して疑いを持ちやすい。 |
| 12. | 病気の症状について詳しく知りたいと思う。 |
| 13. | 自分の体の状態を頻繁にチェックする。 |
| 14. | 健康に関する問題で日常生活が影響を受けることがある。 |
| 15. | 健康診断や医療検査を頻繁に受ける。 |
| 16. | 体の些細な変化が気になって仕方ない。 |
| 17. | 病気の話を聞くと自分も同じ病気かもしれないと考える。 |
| 18. | 病気になることへの恐怖が強い。 |
| 19. | 家族や友人に健康について安心させてもらうことが多い。 |
| 20. | 医師の診断結果に安心できないことがある。 |
| 21. | 病気に対する不安で夜眠れないことがある。 |
| 22. | 健康に関する問題でストレスを感じることが多い。 |
| 23. | 症状が消えても、また現れるのではないかと心配する。 |
| 24. | 病気についての情報を集めるのが習慣になっている。 |
| 25. | 病気になることを考えるとパニックになることがある。 |
| 26. | 健康についての心配で趣味や仕事に集中できないことがある。 |
| 27. | 健康不安で医師に何度も相談することがある。 |
| 28. | 症状があると、すぐに深刻な病気だと思ってしまう。 |
| 29. | 病気になることを避けるために特定の行動を避けることがある。 |
| 30. | 自分の健康不安が過剰だと感じることがあるが、どうしても止められない。 |
| 31. | 健康不安で日常生活に支障をきたしていると感じることがある。 |
| 32. | 病気に関するドキュメンタリーや番組を避けることが多い。 |
| 33. | 健康に関する不安で食事や運動の習慣を過剰に気にすることがある。 |
| 34. | 他人の健康状態についても過度に心配することがある。 |
| 35. | 健康不安が原因で社会的な活動を避けることがある。 |
これらの質問に「はい」が多い場合、病気不安症の可能性が考えられます。しかし、これはあくまでセルフチェックであり、正式な診断には専門家の評価が必要です。病気不安症が疑われる場合は、精神科医や専門のカウンセラーに相談することを強くお勧めします。
疾患回避型不安障害
「疾患回避型不安障害(Disease Avoidant Anxiety Disorder)」は正式な診断名ではなく、近年の研究や臨床現場で使われ始めた概念的な用語で、主に病気不安症と区別される“回避型”の特性を強調したケースに対して使われることがあります。
■ 疾患回避型不安障害とは?
「疾患回避型不安障害」とは、“自分が病気にかかること”への強い不安や恐怖から、病気に関係するあらゆる情報や場面を “徹底的に回避” しようとする心理状態・行動パターンを指します。
「疾患回避型不安障害」は、病気に対する不安が強いにもかかわらず、それを正面から認識することを避けようとする防衛的な反応に特徴があります。臨床的には、“健康不安を訴えない人の裏にある”回避された不安として理解することが重要です。
※DSM-5やICD-11にはこの名称の公式な診断項目はありません。
■ 病気不安症との主な違い
| 特徴 | 病気不安症(Illness Anxiety Disorder) | 疾患回避型不安障害(Disease Avoidant Type) |
| 中心的な不安 | 「今、自分は重病かもしれない」 | 「病気になるのが怖すぎて、それを考えるのも嫌」 |
| 行動傾向 | 医者に何度もかかる、健康チェック、情報を探す | 病院を避ける、健康番組・医学情報も避ける |
| 情報への態度 | 情報を求めすぎて過敏に反応 | 情報を見ること自体が恐怖で、なるべく触れないようにする |
| 主な心理 | 不確実性を埋めようとする“コントロール欲求” | 不確実性を避ける“回避と否認”が中心 |
■ 例(対比)
- 病気不安症:
「この咳、もしかして肺がん? もう1回病院行こう。ネットでも調べてみよう。」 - 疾患回避型:
「また健康診断の案内か…嫌な気分になる。もう見たくない、ゴミ箱に捨てよう。」
■ 関連する障害・概念
この疾患回避型のパターンは、以下の診断に“近縁”あるいは“併存”することがあります。
- 回避性パーソナリティ障害
→ 恐怖への過敏さと回避傾向 - 特定の恐怖症(nosophobia:病気恐怖症)
→ がんやエイズなど「特定の病気」に対する恐怖 - 不安症スペクトラム障害
→ 不安傾向全体の中で、健康に関する側面が強調されている
■ 研究的な位置づけ
この概念は、以下のような潮流の中で注目されています。
- 健康不安のスペクトラム的理解:
「過剰チェック型(病気不安症)」と「過剰回避型(疾患回避型)」の両極 - サイバーコンドリア(ネット検索による不安悪化)に対する回避型反応もその一例
- DSMの診断枠を超えた、機能的診断・行動パターン分類の流れ
病気不安症 と疾患回避型不安障害の比較
気不安症(Illness Anxiety Disorder)と疾患回避型不安障害(Disease Avoidant Anxiety Pattern)の比較表を示します。臨床現場での理解や、見立ての際の参考として活用できます。
実際、病気不安症と疾患回避型不安傾向は、表に出る行動が正反対であるにもかかわらず、根底の不安や動機が酷似しているために見分けが非常に難しく、臨床家であっても混同しやすい領域です。
臨床的ヒント
- 病気不安症は「見すぎる人」だが、疾患回避型は「見ない人」。
- どちらも根底にあるのは“病気=恐怖や崩壊”という信念。
- 両者はスペクトラム上にあり、同一人物が行ったり来たりすることもある。
- 病気不安症の方は、「分かっても安心しない」という苦しさ。
- 疾患回避型の方は、「分かったら壊れる気がする」という苦しさ。
どちらも「病気と向き合う」ことへの耐性の脆さや、存在の安定感の揺らぎが背景にあります。
ただその耐え方が「近づいてでも確かめたい」か「絶対に見たくない」かで、現れ方が全く違ってしまいます。
病気不安症 vs 疾患回避型不安障害:比較表
| 項目 | 病気不安症(Illness Anxiety Disorder) | 疾患回避型不安障害(Disease Avoidant Anxiety Pattern) |
| 定義 | 自分が重篤な病気にかかっている、あるいはかかるのではないかという強い不安に支配される | 病気に関する情報・体験・検査・話題などを、強い不安や嫌悪から回避する傾向 |
| 不安の対象 | 「すでに病気かもしれない」「将来的に重篤な病気になる」 | 「病気を知ること自体」「病気という現実に直面すること」 |
| 主な行動 | 医者への頻回な受診、検査の要求、ネット検索、過剰な身体チェック | 健康情報の回避、医療機関の回避、症状の否認、検診の先送り |
| 身体感覚への注目 | 微細な違和感に敏感、注意が集中する | 身体感覚から注意をそらす、違和感を意図的に無視する傾向 |
| 情報との関係 | 情報を収集し過ぎて不安が増す(サイバーコンドリア) | 情報自体を忌避し、見ない・聞かないことで心理的安定を保つ |
| 受診傾向 | 過剰な受診やセカンドオピニオンの繰り返し | 必要な受診をも避ける、または検診を何年も受けていないことも |
| 心理的防衛 | 「確かめて安心したい」→ 過剰な確認(コントロール欲求) | 「見たくない・知りたくない」→ 回避・否認(防衛的な回避) |
| 診断上の位置づけ | DSM-5・ICD-11に記載された正式な診断カテゴリ | 正式な診断名ではなく、臨床的に整理された概念・傾向分類 |
| 併存しやすい障害 | 強迫症、全般性不安症、うつ病 | 回避性パーソナリティ障害、特定の恐怖症、否認的な不安症 |
| 治療方針 | CBT(認知行動療法)、曝露と反応妨害、医師との一貫性ある連携 | 安全な環境下での「曝露」「感情認識の支援」「回避行動の理解と対処」 |
| 心理教育の方向性 | 「確認しすぎが不安を強める」ことの理解と調整 | 「見ないことで不安が温存される」ことへの気づきと接近の支援 |
| 患者の自己認識 | 「自分は病気かもしれない」ことを強く信じる | 「病気が怖いとは言いたくないが、情報には近づきたくない」 |
| 回避か確認か | 「確認」に突き動かされる | 「回避」に突き動かされる |
簡易的な対比まとめ
| 特徴 | 病気不安症 | 疾患回避型 |
| 行動 | 近づく(調べすぎ) | 避ける(見たくない) |
| 動機 | 確かめたい | 知らずにいたい |
| 不安対象 | 今かかっているかも | 知ったときの衝撃や崩壊感 |
| 主な防衛 | コントロール・確認 | 否認・回避 |
疾患回避型不安障害のセルフチェックリスト
疾患回避型不安障害(Disease Avoidant Anxiety Pattern)の傾向をチェックするための非診断的セルフチェックリスト(40問)です。医療診断ではなく、自己理解や心理面接の補助としてご活用ください。
各項目について、0:まったくあてはまらない、1:あまりあてはまらない、2:ある程度あてはまる、3:非常によくあてはまる、の4段階でお答えください。
| № | 疾患回避型不安傾向 セルフチェックリスト(全40問) |
|---|---|
| 【A. 病気への回避傾向】(10問) | |
| 1. | 健康番組や医学情報を意図的に避けることがある |
| 2. | 検診や健康診断の案内を見ると気が滅入る |
| 3. | 病院の前を通ると緊張したり不快感を覚える |
| 4. | 自分の体調のことを人に聞かれるのが苦手だ |
| 5. | 「病気」という言葉自体に不安や嫌悪感がある |
| 6. | 体調が悪くても、できるだけ病院に行かずに済ませようとする |
| 7. | 健康に関する書籍・記事にあまり触れたくない |
| 8. | 医療ドラマや手術シーンなどが苦手で避けている |
| 9. | 病気の話題が出ると、自然と別の話題に変えたくなる |
| 10. | 検査を勧められると、頭の中が真っ白になったり混乱する |
| 【B. 不安と恐怖の背景】(10問) | |
| 11. | 病気が怖いというより、「病気を知るのが怖い」と感じる |
| 12. | 自分が病気だとわかったら、全てが崩れる気がする |
| 13. | 病気を考えすぎると眠れなくなることがある |
| 14. | 「知らぬが仏」と思うことがよくある |
| 15. | 「もし重大な病気だったら」と考えると、頭がパニックになる |
| 16. | 不安になると、現実逃避的に考えるのをやめたくなる |
| 17. | 健康の話題に触れると、なんとなく縁起が悪い気がする |
| 18. | 「健康に関心を持つ=病気になる前兆」とどこかで感じている |
| 19. | 体の感覚を観察するのが怖くなることがある |
| 20. | 将来の健康状態について考えると、暗い気持ちになる |
| 【C. 回避による行動パターン】(10問) | |
| 21. | 健康診断を後回しにする癖がある |
| 22. | 体調不良があっても、気づかないふりをすることがある |
| 23. | 医者に「異常はありません」と言われても、安心するより困惑する |
| 24. | 体の変化に気づかないように無意識にしていると感じる |
| 25. | 人の病気の話を聞いて、自分に当てはめないようにしている |
| 26. | 病気を予防する努力(運動・食事)も気が重くて避けがち |
| 27. | 健康情報を目にすると、すぐページを閉じたくなる |
| 28. | 体のサインを感じたとき、それが怖くて逆に無視してしまう |
| 29. | 定期検査を「受けた方がいいのはわかっている」が、受けたくない |
| 30. | 健康不安を感じると、現実逃避や娯楽に逃げがち |
| 【D. 自分との関係・信念】(10問) | |
| 31. | 自分は心配性というより「敏感すぎる」と感じる |
| 32. | 健康や死について考えると、存在自体が不安になる |
| 33. | 病気になったら、自分の価値が失われるように思う |
| 34. | 「知らなければ病気じゃない」と思ってしまう |
| 35. | 周囲の人に心配されること自体が苦手だ |
| 36. | どこかで「病気になる自分は許せない」と思っている |
| 37. | 無力感や不完全感に耐えるのが難しい |
| 38. | 自分の身体は信用しづらいと感じている |
| 39. | 病気になったら誰にも頼れないと感じている |
| 40. | 健康を守ることより、病気を知らないで済ますことを優先している |
評価
- 回答を合計し、次のスコア区分で傾向を読み取ってください。
| 合計点 | 傾向 |
|---|---|
| 0-30点 | 回避傾向は非常に少ない。病気への適切な態度を保っている。 |
| 31-55点 | やや慎重な傾向あり。情報回避や検査回避が出ることも。 |
| 56-80点 | 中程度の疾患回避傾向あり。不安の裏に強い恐れがあるかも。 |
| 81-105点 | 明確な疾患回避傾向あり。現実回避や心理的防衛が強く出ている。 |
| 106-120点 | 高度な回避傾向。病気を知ること自体が強い脅威となっている可能性あり。心理的サポートを検討してもよい段階。 |
活用のヒント
- クライエントとの面接ツールとして、どの領域で不安が強く出ているかを可視化できます。
- 各セクションの高得点部分は、回避されている主な感情や行動のヒントになります。
- 「なぜ病気そのものより、“それを知ること”が怖いのか?」という探究にもつながります。
変換症(転換性障害) vs.身体症状症 vs. 病気不安症の違い
3つの疾患はすべて「身体症状を伴う精神疾患」ですが、それぞれ異なる特徴があります。
| 特徴 | 変換症(転換性障害) | 身体症状症 | 病気不安症 |
|---|---|---|---|
| 主な症状 | 神経症状(運動・感覚異常、麻痺・失声・けいれんなど) | 身体症状の持続的な痛みや不調 | 強い病気への不安 |
| 検査結果 | 神経学的異常なし | 医学的説明がつかないことも | ほぼ正常 |
| 不安の対象 | 症状そのものは気にしない | 症状の重症度を過大評価 | 病気の可能性を強く恐れる |
| 診察行動 | 医療より心理的要因が重要 | 何度も医師を受診 | 検査を繰り返し受ける |
| 主な治療 | 心理療法(CBT, リハビリ) | 心理療法+薬物療法(抗うつ薬) | 認知行動療法(CBT) |
| まとめ | 神経症状(運動機能・感覚異常、麻痺・失声など)が突然出現するが本人はあまり不安を感じない。 | 痛み・疲労などの身体症状を過度に心配し、何度も受診する。 | 「病気にかかっているのでは?」という不安が強いが、身体症状は少ない。 |


「疾患回避型不安障害:診断から治療まで」(高野 恵美子、2020年)
「回避の心理学:病気・不安・トラウマ・不調」(村上 純、2018年)
「疾患回避型不安障害:DSM-5からICD-11へ」(山崎 慎、2019年)
「疾患回避型不安障害の治療」(小堀 裕之、2021年)
尾崎紀夫・三村將・水野雅文・村井俊哉:標準精神医学第8版/医学書院