カール・グスタフ・ユングの夢分析
ユングの夢理論は、フロイトのように夢を個人の無意識的な欲求や抑圧された願望の表現として捉えるのではなく、夢を心理的な成長や個人的な意味づけに関わるものとして考えています。

ユングの夢分析は、「個人的無意識」に注目していて個人の経験や生活に由来する無意識の領域であり、その人自身が経験したことや記憶していることが、その人の個人的無意識の内容を反映していると考えています。
ユングは夢の解釈に際して、患者が自分自身で解釈することを重視しました。これは、夢のイメージが個人的無意識の意味を持っているため、患者自身がその意味を理解することが重要であるという考え方からです。ユングは、夢の解釈はセラピストが行うものではなく、むしろセラピストは患者の自己理解を促進する役割を担うとしていました。
また、ユングによれば、夢は個人的な体験や感情を表現するだけでなく、文化的・歴史的・宗教的な要素も含み、人間の共通的な心のあり方を反映することがあるとされます。ユングはこのような共通的な心のあり方を「集合的無意識」と呼び、夢は集合的無意識から現れるイメージやシンボルを含んでいると考えました。
ユングの理論において、夢は個人的無意識や集合的無意識といった無意識の深層部分から発生し、それらの領域に関する情報や意識化されていない欲求や衝動を表現するものと考えられています。
また、ユングは夢に「補償機能」があると考えました。すなわち、意識的に欠けているものや必要なものが夢に現れることで、無意識の側面が意識に取り入れられることでバランスが取れ、心の健康に役立つという考え方です。
さらに、ユングは夢を解釈する際に、夢のイメージを単なる象徴として捉えるのではなく、「元型」と呼ばれる普遍的なイメージに注目しました。元型とは、人間が生まれつき持っている共通的なイメージやシンボルのことであり、夢に現れるイメージやシンボルはこの元型に基づいているとされます。
- 個人的無意識 (Personal Unconscious)
-
定義と役割
個人的無意識とは、主に個人の経験に基づく無意識の領域を指します。これには、日常生活の中で忘れられた記憶や抑圧された感情、未解決のコンプレックスなどがあります。
個人的無意識の内容は、その人の個人的な体験に基づいており、他者とは共有されないものです。夢分析での重要性
夢の中では、個人的無意識の内容がシンボルとして表現されることが多くなります。これらのシンボルは、日常生活で抑圧されている感情や解決すべき課題を象徴的に示しています。たとえば、仕事での不安が夢の中で追いかけられるという形で現れることがあります。ユングの考え方
ユングは、この個人的無意識の内容を理解することで、自分の内的な葛藤やコンプレックスを認識し、解決に向けて取り組むことができると考えました。 - 集合的無意識 (Collective Unconscious)
-
定義と役割
集合的無意識とは、個人を超えた普遍的で遺伝的な無意識の領域を指します。これは、すべての人類に共通する先祖代々の経験や文化的記憶が蓄積されたものです。集合的無意識には、「元型(アーキタイプ)」と呼ばれる普遍的なイメージやシンボルがあります。元型(アーキタイプ)について
元型は集合的無意識の中核を成すもので、夢の中で頻繁に現れます。代表的な元型には次のようなものがあります。- アニマ(Anima):男性の無意識に存在する女性性。
- アニムス(Animus):女性の無意識に存在する男性性。
- シャドウ(Shadow):抑圧された、否定的な側面を象徴。
- 自己(Self):全体性や調和を象徴。
夢分析での重要性
夢の中の象徴が個人的無意識を超えて集合的無意識に関連している場合、それは普遍的なテーマ(例:生と死、再生、英雄の旅など)を扱っていることが多くなります。ユングは、これを理解することで、個人が普遍的な意味や人生の全体性に近づくと考えました。 - 補償機能 (Compensation Function)
-
定義と役割
補償機能とは、意識と無意識のバランスを取るために夢が果たす役割を指します。ユングによれば、夢は、意識的な態度や行動に対する無意識の「補足」や「修正」を提供します。
たとえば、意識が非常に自信過剰になっているとき、夢は失敗や不安を象徴するイメージを提示し、バランスを取ろうとします。夢分析での重要性
補償機能に注目することで、夢がその人の心理的状態にどのように影響を与えているかを理解できます。具体例として- 例1:現実で過度に成功を追求している人が、夢の中で挫折や失敗を経験する。
- → 無意識が過剰な自己信頼を補正し、謙虚さを取り戻させようとしている。
- 例2:意識的に問題から目を背けている人が、夢で恐怖や葛藤に直面する。
- → 問題に向き合う必要性を示唆している。
3つの概念の相互作用:夢分析の流れ
- 夢の内容が個人的無意識に由来している場合
- 個人的な体験や抑圧された感情に目を向けることが求められる。
- 夢が集合的無意識の元型を含む場合
- 人生の普遍的テーマや深層心理の探求に役立つ。個人を超えた視点での理解が重要となる。
- 夢が補償機能を示す場合
- 意識的な態度を無意識がバランスする働きを示唆。心理的な調和を目指すための手がかりとなる。
- 例1:現実で過度に成功を追求している人が、夢の中で挫折や失敗を経験する。
ユングの夢分析
ユングの夢分析は、夢を無意識の内容を探るための重要なツールとして扱い、個人の自己成長と統合に役立てる方法論です。その手順は一連のステップに分かれており、クライエントの文脈を考慮しながら柔軟に進められます。ユングの夢分析の一般的な手順を詳細に解説します。
目的
夢の記録は夢分析の基礎となるステップです。夢を鮮明に記録することで、夢に現れる象徴やテーマを後から正確に分析できます。
実践方法
- クライエントには、夢を覚えている限りできるだけ詳細に記録するよう求めます。
- 時間、場所、登場人物、出来事、感情、印象などを記載します。
- 覚えている夢が部分的であっても、断片的に記録することを奨励します。
目的
夢を一つの物語として全体的に理解することで、その構造やテーマを掴みます。
実践方法
- 夢を物語や映画のように読み解き、登場人物や展開に注目します。
- クライエントに夢の「全体的な雰囲気」について質問します(例:「その夢にはどのような感情がありましたか?」)。
- 夢の始まりと終わりを確認し、流れを明確にします。
目的
夢の中の象徴やイメージに対して、クライエント自身の個人的な連想を引き出します。
実践方法
- 夢に登場する人物、物、シンボルに対して、「このイメージはあなたに何を連想させますか?」と質問します。
- 例:「この動物はあなたにとってどんな意味がありますか?」
- クライエントの過去の体験や感情に関連づけて考えます。
- 重要なのは、セラピスト自身が象徴の意味を決めつけず、クライエントの主観を尊重することです。
目的
夢の象徴が、個人的な連想に加えて、文化や普遍的な意味を持つ場合を考慮します。
実践方法
- ユングの「元型」の概念を用いて、集合的無意識に関連する普遍的な象徴を検討します。
- 例:「蛇」はしばしば変容や再生を象徴する。
- 神話、伝説、宗教、文化的背景に照らして象徴を理解します。
- クライエントに「この象徴はあなたの人生でどのような役割を果たしていると感じますか?」と問いかけます。
目的
夢が意識的な態度に対してどのように補償的に働いているかを探ります。
実践方法
- 現実の生活でのクライエントの意識的な態度や行動を振り返ります。
- 夢がその態度や行動をどう補償しているかを検討します。
- 例:現実で強気に振る舞うクライエントが、夢の中では弱さや恐怖を感じている場合、無意識が「バランスを取ろう」としている可能性があります。
- クライエントに、夢の内容が現在の生活にどのような関連があるかを考えさせます。
目的
夢に現れる元型や集合的無意識のテーマを探り、より深い洞察を得ます。
実践方法
- 夢に登場する象徴が、元型(英雄、影、母、自己など)に該当するかを検討します。
- クライエントと共に、その元型が現在の人生においてどのような意味を持つのかを考察します。
- 例:英雄の夢は、困難に立ち向かう準備が整っていることを示す場合があります。
目的
夢の中で感じた感情を深掘りし、その心理的な意味を探ります。
実践方法
- クライエントに「夢の中でどのような感情を感じましたか?」と尋ねます。
- 夢の中の感情が、現実の生活や内面的な状況にどう関連しているかを考えます。
- 感情が抑圧されている場合は、その理由を探り、無意識とのつながりを明らかにします。
目的
夢のメッセージを現実の生活に統合し、具体的な変化を促します。
実践方法
- クライエントに、「この夢のメッセージをどう解釈しますか?」と問いかけます。
- 夢から得た洞察を基に、現在の課題や決断にどう活かせるかを話し合います。
- 行動計画や意識的な態度の変化を具体化します。
目的
夢のパターンや繰り返されるテーマを観察し、無意識からの長期的なメッセージを探る。
実践方法
- 定期的に記録された夢を分析し、繰り返し現れるシンボルやテーマを確認します。
- 長期的な心理的成長のプロセスや方向性を把握します。
ユングの夢分析の意義
ユングの夢分析は、クライエントが無意識と対話し、自己をより深く理解し、心理的統合を目指すプロセスです。これにより、意識と無意識が調和し、クライエントはより充実した生き方を見出すことができます。この手法は柔軟であり、クライエントの個別性や人生の文脈に応じて応用されます。
※ユングの夢分析の基本的な手順です。ただし、ユングは夢分析において、個人的な解釈や洞察が重要であると考えており、統一的な方法論を提唱していません。そのため、ユングの夢分析は、解釈者と被解釈者の個人的な理解と洞察によって形成されることが多いといわれています。
元型(アーキタイプ)とは
ユングの元型理論は、個人を超えた普遍的なテーマに基づいて人間の心理を探るものです。元型のイメージやシンボルは、夢や芸術、神話を通じて現れ、私たちに自己理解と成長の道筋を示します。心理療法では、これらの象徴を通じて無意識の内容を統合し、全体性に向かうプロセスを支援します。夢分析では、「元型(アーキタイプ)」は、夢の解釈や心理療法において中心的な役割を果たします。
定義
元型とは、集合的無意識の中に存在する普遍的で象徴的なイメージやテーマのことです。元型は個人の経験に基づくのではなく、人類全体に共通する深層心理のパターンとして存在しています。これらは、文化や時代を超えて神話、伝説、宗教、芸術、夢に現れます。
- 普遍性
元型は、全世界の文化や時代に共通して見られます。たとえば、「英雄」「母」「影」などのテーマは、世界中の神話や物語に現れます。 - 象徴性
元型は抽象的な概念を象徴として表現します。これらは直接的な意味を持つのではなく、多層的な意味を秘めています。 - 潜在的構造
元型そのものは潜在的な心理的構造ですが、夢や神話、アートなどを通じて具体的な形を取ります。
主な元型とそのイメージ
ユングが特に重要視した元型と、それに対応する象徴やシンボルを示します。
元型のイメージやシンボルの重要性
- 夢における役割
- 夢の中で元型が表現されることで、普遍的なテーマに触れる機会を得ます。これにより、個人の問題が全体的な文脈で理解され、解決の手がかりが得られる可能性があります。
- 象徴の多義性
- 元型の象徴は一つの意味に限定されず、見る人の状況や心理状態によって異なる意味を持ちます。ユングは、夢の象徴を固定的に解釈するのではなく、個人の文脈に即して柔軟に理解することを重視しました。
- 心理療法での応用
- 元型を通じて、クライエントが自分自身の無意識と向き合い、深層心理を探求することを促します。たとえば、シャドウを受け入れることで自己の統合が進み、自己の元型とつながることで全体性に向かいます。
心理療法における元型の応用
ユングの心理療法では、次のような手法で元型が活用されます。
- 夢分析
元型的なシンボルが現れる夢を解釈し、クライエントの心理的課題や成長の方向性を探ります。 - アクティブ・イマジネーション(Active Imagination)
クライエントが意識的に元型のイメージと対話することで、無意識の内容を統合する作業を行います。 - 芸術療法
絵画や箱庭などの創作活動を通じて、元型の象徴を表現し、深層心理にアクセスする手助けをします。
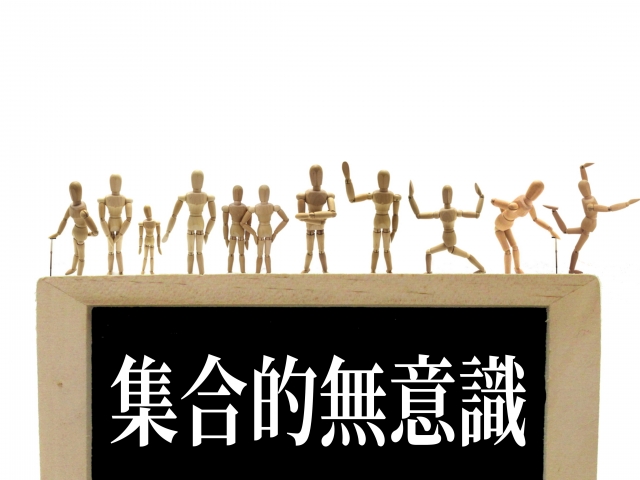
ゲシュタルト心理療法の夢分析
「ゲシュタルト心理療法」の夢分析は、夢を自分で表現し、それを掘り下げ、自己の深層心理にアプローチしていて、夢を「私の夢」として捉え、自分自身の内面にアプローチすることを重視します。セラピストは、クライエントに対して解釈や分析をすることはありませんが、クライエントが深層心理にアプローチするための必要な手段を提供し、クライエントが自分自身の答えを見つけることを支援します。
パールズのゲシュタルト療法
パールズのゲシュタルト療法では、夢は「未解決の問題」や「未熟な感情の表出」として理解されます。夢は、自己を全体的に見つめ直す機会を提供し、心の中にある問題や未解決の感情を浮き彫りにしてくれます。このように、夢は自己理解を深め、成長や癒しにつながる重要な手段とされます。
パールズのゲシュタルト療法の夢分析では、夢の中で現れる人や物、雰囲気や空間などのイメージを、個別の要素から切り離すことなく、全体として捉えます。これは、ゲシュタルト療法の基本的な考え方でもあります。具体的には、夢の中でのイメージを、そのまま人格の部分として捉え、その部分を自己と関連づけ、自己との対話を通じて自己を深く理解することを目的としています。
夢の中で現れるイメージや物の背後に隠れた感情や思考を探求することで、自己の中にある未解決の問題や感情、認識の歪みを浮き彫りにし、自己の成長や癒しにつながる新たな視点や解決策を見つけ出すことができます。また、パールズのゲシュタルト療法では、夢を通じて自己の中にある「未熟な感情」を表出させ、そこから学びを得ることが重要視されます。
夢の中での自己表現を深く理解することで、自己の中にある未解決の問題や感情に対峙し、解決策を見つけ出すことができます。そして、その結果、自己の成長や癒しにつながるとされています。
次は具体的な手順の例です。
患者は、夢をできるだけ詳細に再体験し、夢の中で起こったこと、感じたこと、思ったことを表現します。ゲシュタルト療法における夢の再体験アプローチは、夢を現在の体験として再生し、その中で感じる感情や体験を探求することを目的としています。
具体的な手順としては、患者は夢を思い出し、その内容をセラピストに説明します。その後、セラピストは患者に夢の中での体験を具体的に再現してもらい、夢の中での出来事や感情を再び体験させます。このとき、セラピストは患者に対して、その感情や体験に関する質問や指示を与えます。例えば、「その感覚をもう一度味わってみて」といった具合です。
このアプローチの目的は、夢の中で表現された患者の感情や心理状態を、現在の体験として再生することで、その感情や心理状態についての理解を深めることにあります。また、夢の中で現れるイメージやシンボルについても探求し、その意味を患者自身が理解することを促します。
再体験アプローチは、患者が夢の中で抱える問題やトラウマを解決するために行います。夢の中で表現される感情やイメージを探求することで、患者は自分自身の内面に向き合い、自己理解を深めることができます。また、夢の中で表現される問題やトラウマを解決することで、現実世界での問題解決にも役立ちます。
患者は、夢の中に出てきた人物、物、場所などの要素を自己投影し、それらを自己の一部として捉えます。ゲシュタルト療法における夢の「自己投影」アプローチでは、夢の中で登場する人物や物事を自己の一部として捉え、その意味を探求することが重視されます。
具体的には、夢の中で出てくる人物や物事に対して、患者に「もしあなたがその人物、あるいは物事だったら、どう感じるだろうか?」と問いかけます。このとき、患者はその人物や物事になりきって感情や思考を表現し、それをセラピストがフィードバックします。この過程で、患者が自分自身に対して無意識に抱いている感情や思考が表出されることが狙いです。
また、夢の中で出てくる人物や物事を、自己の内面にある別の側面や反対の側面として解釈することもあります。例えば、夢の中で登場する自分の親友は、自己の内面にある友情や仲間といった側面を表していると考えることができます。一方、夢の中で登場する自己の敵は、自己の内面にある競争心や攻撃性といった側面を表していると解釈することができます。
このように、夢の中で出てくる人物や物事を自己の一部として捉え、自己の内面にある様々な感情や思考を表出させることで、患者が自己をより深く理解し、自己成長を促進することがゲシュタルト療法の目的のひとつとなっています。
夢のディスカッションアプローチは、患者とセラピストが夢の中で起こったことについて話し合い、患者が夢で表現された感情や思考について深く掘り下げます。これは夢の中に登場する様々な要素についての対話やディスカッションを通じて、夢自体により深い理解を与えようとするアプローチとなります。
このアプローチでは、夢に登場するキャラクターやシンボル、場所などの要素を、別々の椅子に置いて、それぞれの要素に対して、患者が自分自身、または他の要素からの視点で話をすることを促します。例えば、キャラクターが犬であれば、先ずその犬について語ってみます。その後、あなたはその犬の視点で、または他の要素から見た犬について語ってみてください。」といった具合です。
このようにして、患者は夢の中で体験した感情や心理的な要素について、より深い理解を得ることができます。また、夢に現れる要素がそれぞれの側面から見えるようにすることで、全体像をより明確にすることができます。
このアプローチは、夢の中に現れる様々な要素を客観的に扱い、それらがどのようにつながっているかを明確にすることで、夢の中に潜むメッセージや自己啓示を理解するのに役立ちます。
患者は、夢の中で出てきた人物や物とロールプレイし、その役割を体験することにより、自己の内面にアプローチします。このように夢分析のロールプレイング・アプローチは、夢に登場する人物や物事の象徴的意味を探求する手法です。このアプローチでは、患者が夢に登場する各要素を自分自身で演じることになります。
具体的には、患者は夢に登場する人物や物事を選び、その役割を演じることになりますが、夢に登場する恋人の役割を患者が演じることで、自分の恋愛観や相手との関係性を探求することができます。
このアプローチでは、患者が夢に登場する要素を自分自身で演じることで、その象徴的意味を自覚することができます。また、演じることで自分自身の気持ちや感情を表出することができ、それを通じて自己理解を深めることができます。
ロールプレイングによって、夢に登場する人物や物事が持つ象徴的な意味を理解することで、患者は自分自身についての新たな気づきを得ることができます。
最後に、患者は、自分が得た気づきや認識をまとめ、今後の行動計画を立てます。クロージング・アプローチは、夢のセッションの最後に行われるプロセスで、夢についてのクロージングステートメントを作成することを目的としています。このアプローチは、夢の象徴的な意味を理解し、自分自身やその他の人や事物についての新しい洞察を得るための手段として用いられます。
このアプローチでは、患者は夢の象徴的な要素を取り出し、それらが自分自身の人生の中で何を表しているかを考えます。患者は、夢の中で自分が取ったアクションや感情についても考えます。そして、夢の中で得た新しい知識や洞察をもとに、自分自身に対して肯定的なメッセージを作成します。
例えば、夢の中で自分が恐ろしい状況に直面して、それに対処するために勇気を出したとしたら、患者は「私は強く勇敢です。」という肯定的なメッセージを作成することができます。
このようなクロージングステートメントは、患者が夢から得た新しい知識や洞察を肯定し、自己価値感を高めるのに役立ちます。また、これにより患者は夢に関連する問題や課題に対処するためのポジティブなアプローチを開発することができます。
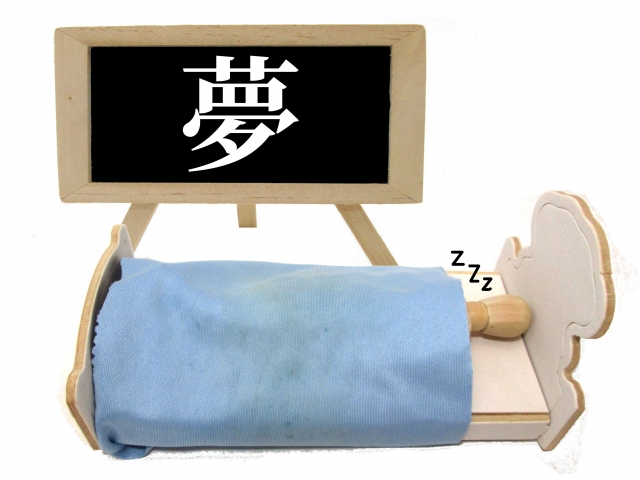
ユージン・ジェンドリン
ジェンドリンは、夢には普通の感情に加えて、分類できない独特の感覚があることに注目しています。「体験過程理論」を提唱し、フォーカシングと呼ばれる技法で感覚に焦点を当て、患者がその感覚を理解し、自己を発見し、発展させるのを助けています。
夢の象徴性や内容を分析する伝統的な夢解釈方法を使用することもありますが、ジェンドリンのアプローチでは、夢を単なる象徴やメタファーの集合体としてではなく、体験そのものとして扱います。つまり、夢の中で感じた感覚や、夢から目が覚めた後に残るフェルトセンスを重視することで、自己の深層心理にアクセスすることを目的としています。
また、ジェンドリンは、夢の内容を忘れたとしても、夢によって残された感覚が重要であるとしています。つまり、夢によって残された感覚をフォーカシングの素材として使用し、その感覚について患者と対話することで、自己理解を促すことができると考えています。
ジェンドリンは、夢をワークに組み込むことで、患者の内面にアプローチし、自己理解を深めることを目的としています。ジェンドリンのアプローチでは、夢を単なるメタファーや象徴の集合体として扱うのではなく、夢によって残された感覚やフェルトセンスを重視し、その感覚に焦点を当てることで、患者の内面にアクセスすることを目的としています。
ジェンドリンは、夢の分析にフォーカシングという技法を用います。フォーカシングは、内省的な状態を作り出す技法で、自己をより深く理解するために使用されます。この技法は、個人的な問題に集中し、その感情的な体験に注意を向け、感情を表現することを助けます。
夢の分析において、ジェンドリンは、夢を再生して体験的に感じ取り、感情や身体感覚にフォーカスすることを提唱しています。夢の象徴性や潜在的な意味を解釈する代わりに、夢の具体的な体験に直接アプローチすることを重視しています。
具体的には、フォーカシングに基づく夢分析では、夢を再生して体験的に感じ取り、夢に登場する人物や物事を身体感覚的に探求します。夢の内容に関する質問は、主に身体感覚的な体験にフォーカスします。例えば、「その感覚はどこにありますか?」、「その感覚はどのような形や色をしていますか?」、「その感覚はどのような動きをしていますか?」などです。
夢分析にフォーカシングを用いることで、夢の象徴性や潜在的な意味を解釈するのではなく、夢に現れた感情や身体感覚をより深く理解することができます。これにより、自己の内面にアクセスし、自己をより深く理解することができるとされています。
ホリスティック・アプローチの夢分析
ホリスティック・アプローチは、人間を身体・心・魂の三つの側面から捉え、夢分析にもそれら全てを含めてアプローチする手法です。次は、ホリスティック・アプローチにおける夢分析の手順の例です。
- 夢の記録
夢をできるだけ詳しく記録します。夢を見た日付や時間、場所、夢の内容、感情、登場人物、出来事の流れなどを記録します。また、夢の中で感じた身体的な感覚や自分自身の役割も重要となります。 - 夢の象徴性の解釈
ホリスティック・アプローチでは、夢の中で現れる象徴やシンボルの意味を解釈することが重要視されます。夢の中で見たものや感じたことには、自分自身が直面している問題や課題を表すことがあるためです。 - パターンの発見
夢を何度か見た場合、その中で繰り返されるパターンやテーマを見つけます。夢の中で何度も繰り返される要素は、その人の生活や心理状態において特定の重要性を持つと考えられます。 - 身体的な感覚の分析
夢には、身体的な感覚を伴うことがあります。ホリスティック・アプローチでは、夢の中で感じた身体的な感覚に焦点を当て、その感覚が何を意味しているかを考えます。例えば、痛みや緊張感は、ストレスや不安を表すことがあります。 - 心の状態の調査
夢は、人間の心理状態を反映することがあります。ホリスティック・アプローチでは、夢を通じて、その人の心理状態を探求します。たとえば、夢の中で自分自身が弱々しい状態にある場合、その人の自己肯定感が低いことを表しているかもしれません。 - 夢の要約
最後に、夢を要約し、それが何を意味するのかを明確にします。夢の中で現れたテーマやシンボルを、その人の生活や心理状態に関連付け、解釈していきます。
アルフレッド・アドラーの夢分析
夢を「人生のスタイルの支持と正当化を提供する」ものと考え、夢を理解することで、個人の心理的側面や人生の目標、価値観を把握することができると考えました。彼は、人間の心理を「個人心理学」という学問分野として研究し、夢を含む様々な心理現象について理論を提唱しました。
アドラーの夢理論によれば、夢は自己表現の手段としての役割を果たすものであり、夢を通して個人が持つ価値観や自己イメージ、人生の目標を反映するとされています。夢は、現実において達成できなかったことを補うための精神的な代償機能を持ち、個人の欲求不満や心の葛藤を解決しようとする試みとして現れるとされます。
アドラーは、夢の内容に着目し、夢に現れる象徴やメタファーを分析することで、個人の無意識的な欲求や心理的な状態を理解しようとしました。彼は、夢の内容が個人の現実的な問題や心理的な課題に関係していることが多いと考え、夢を解釈することで、個人の問題解決能力を高め、自己実現のプロセスを促進することができるとしたのです。
アドラーの夢理論は、フロイトのような性的な欲求や心的トラウマといった要素を排除し、現実的な問題解決や自己実現に焦点を置いた理論です。彼は、夢が個人の人生目標や価値観を表現し、自己実現のプロセスを促進する手段として重要であると考えていました。
アドラーは、夢を人生のスタイルと支持し、自分自身の行動に正当化を与える手段として見ています。夢は個人の内的な気持ちや願望を表現する方法であり、過去の出来事や現在の問題に対する個人的な解決策を探るための手段でもあります。
また、アドラーは夢における感情を重視しており、夢の目的は、感情的なストレスを解消し、それに対する個人的な対処方法を見つけることだと考えています。夢の中での体験は、現実とは異なるものであるため、自己陶酔的な体験を可能にし、自己催眠的な状態を作り出すことができます。
総じて言えることは、アドラーの夢理論では、夢は個人の内的な状態を表現する手段であり、現実的な解決策を探るための手段でもあると考えられています。また、夢は個人の感情的なストレスを解消するために役立ち、自己陶酔的な状態を作り出すことができます。

『夢と無意識』(S.フロイト)
『夢分析入門』(C.G.ユング)
『夢分析と心理療法』(M.フォン・フランツ)
『夢と瞑想』(A.ハフマン)
『ゲシュタルト療法と夢』(G.ドラーマー)
『現象学と夢』(A.ヘルマン)
『元型的心理学の理論と実践』(J.ヒルマン)

