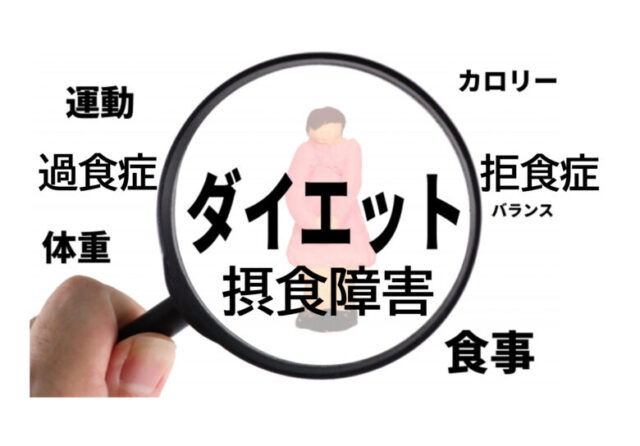神経性やせ症・神経性過食症など摂食症の要因・症状・診断・身体の健康に及ぼす影響と治療法の知識
摂食障害(摂食症)は、心理的背景を持つ食行動の障害で、摂食行動に問題を抱えていて、健康に深刻な影響を与える疾患です。
神経やせ症は、神経性無食欲症・神経性食欲不振症や拒食症とも呼ばれ、摂食量が極端に減少し、過度の体重減少が見られる疾患です。神経やせ症の原因については複数の要因が考えられていますが、食への恐怖や自己評価の歪みが特徴的です。
神経性過食症は、神経性大食症や過食症ともよばれ、暴食行動は、ストレス、不安、寂しさ、悲しみなどの感情的な要因に影響を受けることがあり、大量の食べ物を短時間で摂取することによって、過食を繰り返す疾患で、過剰な食べ物を摂取することによって、食べ物に対するコントロールができない状態が特徴的です。
これらの疾患は、心理的・社会的・生物学的要因が絡み合って引き起こされると考えられています。例えば、完璧主義やコントロール欲求が強い人や、体型・外見に関する不安を抱える人、トラウマ経験がある人、また家族内の人間関係の問題や社会的なストレスなどが関与することがあります。
摂食障害の歴史は古く、過去には女性の食欲抑制が美徳とされる時代がありました。現代でも、メディアや社会的な圧力によって、スリムな体型が美徳とされ、過度なダイエットや運動、過食・嘔吐などが増加する傾向があります。
摂食障害の治療は、心理療法や薬物療法、栄養療法などがあり、病状に応じた治療法が選択されます。また、早期発見や早期治療が重要であり、専門家の診断と適切な治療が必要です。
年齢層は、かつては10代が中心でしたが、最近では思春期以降の長期化や成人まで、そして小学生の発症も見られるようになっています。これは、社会的なストレスや美容に関する意識の高まり、そしてSNSなどによって他人との比較が増えたことなどが原因の1つとされています。
神経性過食障害が神経性やせ症よりも年齢層が高いのは、社会的なストレスやうつ病、不安障害などが原因とされています。また、摂食障害は身体症状も様々なため、精神科や心療内科以外にも内科や小児科、皮膚科などで受診することがあるとされています。
摂食障害は、過度な食事制限や過食・嘔吐などによって、健康に深刻な影響を与えるため、早期の治療が必要となります。また、家族や友人が早期に気づくことも大切であり、専門家の診断と治療が適切に行われるようにすることが重要です。
このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

拒食症
神経やせ症(拒食症)
摂食障害は、食事摂取に関する異常な行動や考え方が特徴的な精神的な障害群です。その中で、「神経やせ症」は、いくつかの異なる用語で呼ばれることがありますが、日本では一般的に「神経性無食欲症」や「神経性食欲不振症」とも呼ばれることがあります。英語では”Anorexia Nervosa”と呼ばれます。
神経性無食欲症(神経性食欲不振症)は、次のような特徴を持つ摂食障害の一つです。
- 極端な体重減少
- 神経性無食欲症の人は、極端な食事制限や過度な運動を通じて体重を減少させることを特徴とします。これは、実際の体重に関わらず、自己評価としては常に過度に太っていると感じているためです。
- 異常な体型への恐れ
- 神経性無食欲症の人は、自分の体形や体重に対して異常なほどの不満や恐れを抱き、それを改善しようと過度な努力をします。
- 自己評価と体重の歪み
- 神経性無食欲症の人は、自分の体重や体形に対する現実と歪んだ自己評価が一致していません。そのため、他人から痩せすぎだと指摘されても、それを認めないことがあります。
- 月経の停止(女性の場合)
- 月経が停止することがあり、これは体重減少と栄養不足による影響です。
- 心理的な側面
- 自己評価への歪んだ考え、過度な体重への恐れ、パーフェクショニズムの強い傾向など、心理的な側面も強調されます。うつ病や不安障害などの症状も一般的です。
神経やせ症は、身体的な健康に深刻な影響を及ぼすことがあり、場合によっては致命的となることもあります。治療には、心理療法や栄養指導、家族のサポートなどがあり、専門家の監督の下で行われることが重要です。早期の介入と治療が、回復の可能性を高める上で重要です。
拒食症の原因
拒食症の原因については複数の要因が考えられていますが、具体的な原因は明確には分かっていません。次に一例を挙げます。
- 社会文化的要因
美の観念やスリムな体型が求められる社会的圧力が拒食症を引き起こす場合があります。 - 精神的要因
過剰なストレス、うつ病、不安障害、トラウマなどが拒食症の発症に関与すると考えられています。 - 家族史や遺伝的要因
拒食症は家族内で起こりやすく、遺伝的な要因が関与している可能性があります。 - 神経生物学的要因
食欲、食物摂取、体重調節に関わる神経伝達物質のバランスの乱れが拒食症を引き起こすことがあります。
以上のような要因が複合的に作用することで、拒食症が発症すると考えられています。ただし、個人差があり、拒食症の発症には複数の要因が関与しているため、一概には言えません。
拒食症が身体に及ぼす悪影響
拒食症は、長期間にわたる栄養不足によって様々な身体的な異常が引き起こされる可能性があります。次はその一例です。
- 低体重や栄養不足によって生じる代謝異常、例えば低血糖症、低カリウム血症、貧血、低血圧、冷感、めまいなど。
- 骨粗鬆症の発症や進行が起こります。これは、カルシウムやビタミンDの不足、またはホルモン分泌異常によるものです。
- 内分泌異常の発症が起こります。例えば、月経異常や無月経、不妊症などが挙げられます。
- 心臓機能の低下が起こります。拒食症の人々は、心臓の筋肉量が減少し、心拍数が低下するため、心臓の働きが弱くなる場合があります。
- 免疫機能の低下が起こります。拒食症の人々は、栄養不足によって免疫機能が低下するため、感染症などにかかりやすくなる場合があります。
- 脱力や筋力低下などの筋肉の損失が起こります。これは、栄養不足によってエネルギーが不足するため、筋肉を消費してエネルギーを補おうとすることが原因です。
- 精神的な問題が起こります。拒食症は、うつ病や不安障害などの精神疾患と関連していることが多く、身体的な問題だけでなく、精神的な問題も引き起こす可能性があります。
これらの身体的な異常は、栄養状態の悪化に応じて重症化することがあります。拒食症の治療には、栄養補給や薬物療法、心理的な支援などが必要であり、早期の治療が重要です。
過食症
神経性過食症(過食症)
神経性過食症は、神経性大食症や過食症とも呼ばれ摂食障害の一種であり、食べ過ぎや暴食行動が特徴的な疾患です。日本では一般的に「神経性過食症」と呼ばれていて、英語では”Binge Eating Disorder”と呼ばれます。
次に、神経性過食症の主な特徴を概要として説明します。
- 暴食行動
- 神経性過食症の人々は、短期間に非常に多くの食物を摂取する暴食行動をします。暴食の際には、通常の食事量をはるかに超える量の食べ物を摂取することがあります。
- 感情的な要因
- 暴食行動は、ストレス、不安、寂しさ、悲しみなどの感情的な要因に影響を受けることがあります。過食は、これらの感情をコントロールしようとする手段としています。
- 無力感
- 暴食の後、罪悪感や恥ずかしさ、無力感が感じられていて、これがサイクルを悪化させることもあります。
- 制御の喪失
- 暴食の際、食べ物を制御できなくなることが特徴的です。つまり、一度暴食が始まると、どれだけ食べたいかをコントロールできなくなります。
- 体重の増加
- 暴食の結果、体重が増加していきます。しかし、神経性過食症の人は、摂取カロリーの増加に対して他の摂食障害と比べて過度に反応することはありません。
神経性過食症は、身体的な健康問題や精神的な苦痛を引き起こす可能性があります。治療には、心理療法(特に認知行動療法や対人関係療法)、栄養指導、ストレス管理などがあります。専門家の指導の下で行われることが重要です。早期の介入と適切な治療は、神経性過食症の管理や回復において重要な役割を果たします。
過食症の原因
過食症の原因は単一の要因ではなく、複数の要因が絡み合っていると考えられています。次に、主な要因をいくつか挙げてみます。
- 心理的ストレス
ストレスが過剰になると、食べ物を欲する欲求が高まることがあります。また、ストレスが原因で、自分自身を責めたり、不安や抑うつ症状を引き起こすことがあります。 - 満腹中枢の異常
食事の量や空腹感を調節する満腹中枢に異常があることが原因の一つとされています。満腹中枢に異常があると、食欲を抑えることができずに過食につながると考えられます。 - 過剰なダイエット
食事制限や運動によるダイエットが過剰に行われると、空腹感や飢餓感が強くなり、過食を引き起こすことがあります。 - 環境要因
家庭環境や社会的な環境が過食症の発症に影響を与えることがあります。例えば、食べ物が豊富にある環境や、食事を一人で食べることが多い環境などがその例です。 - 遺伝的要因
過食症には、遺伝的要因が関与している可能性があります。特に、脳内物質のバランスを調節するセロトニンやドーパミンといった遺伝子が関与しているとされています。
これらの要因が複合的に絡み合って、過食症が発症すると考えられています。ただし、個人差が大きく、必ずしもこれらの要因が全て当てはまるわけではありません。
過食症が身体に及ぼす悪影響
過食症は、身体に多くのダメージを与える可能性があります。次は一般的な身体的な症状やダメージの例です。
- 肥満や過体重
過食症は、多量のカロリーを摂取するため、肥満や過体重の原因になります。 - 消化器系の問題
多量の食物を摂取することは、胃や腸の消化器系に負荷をかけます。それによって、消化器系のトラブルや問題を引き起こす可能性があります。例えば、腹痛、胃酸逆流、下痢、便秘などがあります。 - 高血圧や心臓病
高カロリーの食事が続くと、高血圧や心臓病のリスクが高まります。 - 糖尿病
過食症の人は、高糖分の食品を過剰に摂取する傾向があるため、糖尿病の発症リスクが高くなります。 - 脂肪肝
過剰なカロリー摂取によって、肝臓に脂肪が蓄積され、脂肪肝の発症リスクが高くなることがあります。 - 関節痛や骨粗鬆症
肥満が続くと、関節や骨に負荷がかかり、関節痛や骨粗鬆症のリスクが高くなることがあります。 - 精神的な影響
過食症は、自己嫌悪や罪悪感、うつ病など、精神的な問題を引き起こす可能性があります。
過食症による身体的なダメージは、個人差がありますが、重度の場合は健康に深刻な影響を与えることがあります。早期の治療が必要です。

摂食症(摂食障害)のデータ
摂食障害の受診率は低く、正確な疫学データを把握するのは困難ですが、日本国内外の研究によって摂食障害に関する疫学データが得られていますので、神経性やせ症、神経性過食症について、次に男女別、年齢層別の疫学データをまとめます。
摂食障害の背景
- 遺伝的要因:遺伝子・脳機能の特性など
- 性格の傾向:完璧主義者・自己肯定感の低さなど
- 環境:競争社会・やせ礼賛・家庭環境など
年齢層別のデータについては、国内外で研究が異なるため、上記のデータは一例であり、その他の研究によって異なる可能性があります。
【神経性やせ症】
- 日本国内では、15~19歳の女性における有病率が0.5~1.0%程度とされています。男性の有病率は女性よりも低く、0.1%以下と報告されています。
- 海外では、アメリカ合衆国が15~24歳の女性における有病率が0.3~0.9%程度、イギリスでは15~30歳の女性における有病率が0.5%程度と報告されています。
- 痩せたい願望が強く、食事を減らしてストレスの解消をしています。
【神経性過食症】
神経性過食症は、埋め合わせとして過度な運動や嘔吐、下剤の使用など不適切な代償行動をします。
- 日本国内では、15~19歳の女性における有病率が0.5~1.5%程度とされています。男性の有病率は女性よりも低く、0.3%以下と報告されています。
- 海外では、アメリカ合衆国が18~59歳の女性における有病率が1.0%程度、イギリスでは16~34歳の女性における有病率が1.5%程度と報告されています。
- 痩せたい願望がありながら、過食をすることでストレスを解消しています。
過食性障害
- 過食性障害は、男女の比は2:3で男性にも珍しくなく、3.5%という報告もあります。
- やさせたい願望が少なく、過食でストレスを解消しています。
【失コントロール感】
神経性過食症の「失コントロール感」とは、過剰な食事摂取行動を抑えることができず、自分自身が食べ過ぎてしまったという感覚のことを指します。食べ過ぎた後に自己嫌悪や罪悪感を感じたり、自分自身を責めたりすることがあります。このような感覚は、神経性過食症の特徴的な症状の一つであり、過剰な食事摂取を繰り返す原因となることがあります。
摂食症の過食排出型・摂食制限型と肥満恐怖
過食排出型の摂食障害
過食排出型の摂食障害(神経性やせ症も含む)は、神経性過食症とも呼ばれ、大量の食物を短時間で摂取する「過食」や、食後に意図的に嘔吐する「自己誘発性嘔吐」、下剤や利尿剤などを乱用する「排泄」などの行動を特徴とします。
- 【嘔吐】
-
神経性やせ症や神経性過食症の人は、食べ物を食べた後に意図的に吐くことがあります。この嘔吐は、消化されていない食べ物を身体から排出するための行動であり、過剰な体重増加を防ぐために行われることがあります。
嘔吐により、消化器系に問題を引き起こすことがあります。また、口内や喉、食道、胃の組織を傷つけることがあります。 - 【下剤乱用】
-
神経性やせ症や神経性過食症の人々は、下剤を不適切な方法で使用することがあります。下剤は、便通を促進し、体内から水分を排出するための薬剤です。
しかし、過剰な使用は、体内の水分と電解質のバランスを乱し、消化器系に損傷を与えることがあります。また、下剤の過剰使用によって依存症が引き起こされることもあります。
摂食制限型の摂食障害
摂食制限型の摂食障害は、神経性やせ症(拒食症)/神経性無食欲症とも呼ばれ、食べ物を極端に制限することで体重を減らすことを目的とする行動が特徴です。食べ物を拒否する、極端に少ない食事しか摂取しない、食事を極端に遅くしたり、あるいは急いで食べることなどが挙げられます。
過食排出型と摂食制限型の摂食障害は、ともに食事に対する異常な関心や行動が現れる病気であり、心身に深刻な影響を与える可能性があります。過食排出型の摂食障害と摂食制限型の摂食障害は、互いに独立して発症することもありますが、同時に存在することもあります。
神経性やせ症における「肥満恐怖」は、肥満になることへの強い恐怖心や不安感を指します。これは、自己評価が過剰に体型や体重に対して影響されることで発生します。具体的には、自分の体重や体型を常に気にし、少しでも体重が増えると不安や恐怖を感じることが挙げられます。また、周囲の人たちからの体型や体重に対する批判的なコメントや、メディアなどで見る「理想的な体型」に対するプレッシャーも肥満恐怖を引き起こす要因になります。これにより、食事を制限したり、過度に運動したりして体重を減らそうとする行動が見られる場合があります。
摂食症(摂食障害)のICD-11による診断基準
神経性やせ症(拒食症)の診断基準
神経性やせ症/神経性無食欲症は、摂食障害の一つで、主に女性に多く見られます。臨床症状としては、以下のような特徴があります。
- 食欲不振や食事量の制限、過度のダイエットなどにより、体重が著しく低下する
- BMI(Body Mass Index:身長と体重の比率)が18.5未満となる
- 自己評価が異常に低く、自己肯定感が低下する
- 月経不順、または月経が止まる
- 疲れやすく、集中力が低下する
- 寒がりやめまい、頭痛、低血圧などの身体症状が出ることがある
ICD-11では、神経性やせ症/神経性無食欲症の診断基準は以下のように記載されています(一部省略あり)
- A) 自己評価の歪みが、自己評価と他者の評価の違いに関連していること。
- B) 体重の減少または低体重(BMI < 18.5 kg/m2)。
- C) 自己評価の歪みがあること。
- D)食欲の減退または欠如、または食べ物の摂取の拒否による体重減少が、年齢、性別、発達レベル、身体状態に不釣り合いであること。
- E) 治療を拒否する、または治療に応じない。
- F) 他の原因による体重減少が除外されていること。
以上の基準に加えて、ICD-11では、自己評価の歪みについて、自己イメージの過小評価、自己否定的な自己認識、または自己肯定感の低下といったものが考えられることも示されています。また、月経不順や肥満恐怖といった特定の症状については、ICD-11の診断基準には明示的に記載されていませんが、臨床評価においては考慮されるべき要素であることが示唆されています。
神経性やせ症(拒食症)のセルフチェックリスト
神経性やせ症(拒食症、Anorexia Nervosa)の自己評価のためのセルフチェックリストを以下に示します。各質問に対して「はい」または「いいえ」で答えてください。
| № | 神経性やせ症(拒食症)のセルフチェックリスト30問 |
|---|---|
| 1. | あなたは自分の体重や体型について過度に気にしていますか? |
| 2. | あなたは体重が増えることを極度に恐れますか? |
| 3. | あなたは自分の体型が太っていると感じることが多いですか? |
| 4. | あなたは体重を減らすために、食事を制限することがありますか? |
| 5. | あなたは食事をすることに対して罪悪感を感じることがありますか? |
| 6. | あなたは他人に自分が食べている量を隠すことがありますか? |
| 7. | あなたは食べた後に、吐いたり下剤を使ったりすることがありますか? |
| 8. | あなたは食事の前後に過度に運動をすることがありますか? |
| 9. | あなたは自分の体重や体型が異常だと指摘されても、それを否定しますか? |
| 10. | あなたは体重が減っても、もっと痩せたいと感じますか? |
| 11. | あなたは低カロリーの食事ばかりを選びますか? |
| 12. | あなたは特定の食べ物を避けることがありますか? |
| 13. | あなたは自分の体重や体型に対する満足感が得られないことが多いですか? |
| 14. | あなたは体重が減ることで、自己価値が上がると感じますか? |
| 15. | あなたは体重や体型に関する考えが頭から離れないことがありますか? |
| 16. | あなたは食事をするときに、非常に少量しか食べないようにしていますか? |
| 17. | あなたは食事の計画やカロリー計算に多くの時間を費やしますか? |
| 18. | あなたは体重が減ることで、他人からの賞賛や評価を期待しますか? |
| 19. | あなたは体重が増えることを避けるために、極端な食事制限を行いますか? |
| 20. | あなたは食事に関するルールを厳格に守っていますか? |
| 21. | あなたは自分の体重や体型に対して過度に批判的ですか? |
| 22. | あなたは食事をするときに、他人の目を気にしますか? |
| 23. | あなたは食べ物についての会話や場面を避けることがありますか? |
| 24. | あなたは体重が減ることで、幸福感や達成感を感じますか? |
| 25. | あなたは食事をするときに、不安やストレスを感じますか? |
| 26. | あなたは食事を抜いたり、極端に少ない量を食べることがありますか? |
| 27. | あなたは体重が減ることで、健康上の問題が生じたことがありますか? |
| 28. | あなたは食事をするときに、自分を厳しく管理していますか? |
| 29. | あなたは食事に対して過度にこだわりがありますか? |
| 30. | あなたは他人が自分の食事や体重について話すのを避けることがありますか? |
このセルフチェックリストは、自己評価の一助として提供されています。多くの質問に「はい」と答えた場合、神経性やせ症の可能性があるため、専門家の診断を求めることをお勧めします。
神経性過食症(過食症)の診断基準
神経性過食症/神経性大食症のICD-11による診断基準は以下の通りです(一部省略あり)。
- A) 一連の期間にわたり、反復的に、食事摂取量が通常よりも著しく増加する。
- B) 食事の摂取が感情的な失コントロールによって特徴付けられる(自分でコントロールできないような感覚)。
- C) 過食時に、次のうち少なくとも1つが起こる。
- ⒈通常よりも早く、大量に食べる。
- ⒉通常よりもゆっくりと、長時間にわたって食べる。
- ⒊食べ過ぎたことに対して、悔恨の念を抱く。
- D) 過食行動は、1週間に少なくとも2回、3か月以上にわたって続いている。
- E) 過食行動により、心身に重大な苦痛または損害が生じている。
- F) 過食行動が、体重増加、肥満、または他の健康上の問題につながる恐れがある。
- G) 過食行動は、他の精神疾患の結果として発生しているものでない。
- H) 過食行動は、他の医学的状態(例:糖尿病、遺伝性疾患)の影響下にあるものでない。
神経性過食症(過食症)のセルフチェックリスト
神経性過食症(過食症、Bulimia Nervosa)の自己評価のためのセルフチェックリストを以下に示します。各質問に対して「はい」または「いいえ」で答えてください。
| № | 神経性過食症(過食症)のセルフチェックリスト30問 |
|---|---|
| 1. | あなたは一度に大量の食べ物を短時間で食べることがありますか? |
| 2. | あなたは過食した後に、自己嫌悪や罪悪感を感じることがありますか? |
| 3. | あなたは体重増加を防ぐために、過食後に自ら嘔吐することがありますか? |
| 4. | あなたは過食後に、下剤や利尿剤を使用することがありますか? |
| 5. | あなたは過食した後に、過度な運動をすることがありますか? |
| 6. | あなたは食べ物の誘惑に抵抗できず、過食を繰り返すことがありますか? |
| 7. | あなたは過食のエピソードが週に少なくとも一度ありますか? |
| 8. | あなたは過食の後に、食べたことを他人に隠そうとしますか? |
| 9. | あなたは過食中に食事のコントロールができないと感じますか? |
| 10. | あなたは体重や体型に対する不満が過食の引き金になりますか? |
| 11. | あなたは過食後に気分が落ち込みますか? |
| 12. | あなたは体重や体型を気にして、極端なダイエットを試みますか? |
| 13. | あなたは過食後に何かしらの方法でカロリーを消費しようとしますか? |
| 14. | あなたは過食することで一時的な快感を感じますか? |
| 15. | あなたは食べ物についての考えが頭から離れないことがありますか? |
| 16. | あなたは過食のエピソードが自分のコントロールを超えていると感じますか? |
| 17. | あなたは体重や体型に関して他人の評価を気にしますか? |
| 18. | あなたは過食の後に自己嫌悪に陥りますか? |
| 19. | あなたは過食を防ぐために食事を抜くことがありますか? |
| 20. | あなたは過食のエピソードが生活に支障をきたしていますか? |
| 21. | あなたは過食のエピソードが特定の感情(ストレス、不安など)に関連していますか? |
| 22. | あなたは過食の後に疲れを感じますか? |
| 23. | あなたは過食の後に体重の増減を頻繁にチェックしますか? |
| 24. | あなたは過食後に飲み物(特に水分)を大量に摂取しますか? |
| 25. | あなたは過食のエピソードが自分の意志に反して繰り返されますか? |
| 26. | あなたは過食の後に友人や家族と過ごすのを避けることがありますか? |
| 27. | あなたは過食のエピソードに対する強い恥ずかしさを感じますか? |
| 28. | あなたは過食のエピソードが頻繁に起こるため、社会的な活動を避けることがありますか? |
| 29. | あなたは過食のエピソードが起こるたびに、自己評価が低下しますか? |
| 30. | あなたは過食のエピソードが長期的な健康問題につながることを心配しますか? |
このセルフチェックリストは、自己評価の一助として提供されています。多くの質問に「はい」と答えた場合、神経性過食症の可能性があるため、専門家の診断を求めることをお勧めします。
神経性やせ症と神経性過食症の治療

神経性やせ症の治療
神経性やせ症の治療には、栄養補充や食事療法、薬物療法、心理療法などのアプローチがあります。一般的には、専門家のチームアプローチによって治療が行われます。
- 食事療法においては、栄養面での改善が重視されます。摂取カロリーを増やし、栄養バランスの良い食事を摂るように指導されます。しかし、過度の食事制限や食べ物に対する恐怖感が強い場合は、徐々に摂取量を増やしていく必要があります。食事療法に加え、栄養補助食品の使用が推奨されることもあります。
- 薬物療法としては、抗うつ薬や抗不安薬などが使われることがありますが、個人差があります。また、これらの薬物は副作用を持つことがあるため、慎重に処方されます。
- 心理療法には、認知行動療法、家族療法、対人関係療法などがあります。認知行動療法では、食事に関する誤った思い込みや、自己評価に関する問題に対処することが目的です。家族療法では、家族との関係性を改善することで治療効果を高めることが狙いです。対人関係療法では、人間関係に焦点を当て、社会的なストレスを緩和することを目指します。
神経性やせ症の治療には、個人差があるため、専門家の指導のもと、適切な治療法を選択する必要があります。
薬物療法
1. 抗不安薬
- セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI): 抑うつ症状や不安症状に対処し、摂食行動の安定を図ることが期待されます。
2. 抗精神病薬
- オランザピン: 食欲を増進させる効果があり、体重増加を促進することが期待されます。
3. 作用メカニズム
- 薬物は脳内の神経伝達物質のバランスを調整し、食欲や情動の制御に影響を与えることが期待されます。
4. 効果
- 薬物療法は神経性やせ症の症状の改善に効果的であることが報告されていますが、個人差があります。
精神療法
1. 栄養指導
- 概要: 栄養士や専門家による個別の栄養指導が該当します。
- 効果: 健康的な食事習慣を身につけ、適切な栄養を摂取することを目指します。
2. 行動療法
- 概要: 摂食行動のパターンやトリガーを特定し、健康的な摂食習慣を養成する治療法です。
- 効果: 健康的な食事行動を促進し、異常な食事制限のパターンを改善します。
併用療法
薬物療法と精神療法を併用することで、摂食行動の安定と、栄養の適切な摂取を促進することが可能となります。
*効果が実証された精神療法は、認知行動療法と支持的な臨床管理です。
治療の選択は患者の状態に応じて調整され、患者と治療チームとの協力が治療に重要です。治療計画は患者の症状やニーズに基づいて個別に調整されるべきです。
摂食障害の入院治療
摂食障害において、重症化した場合や治療が困難な場合は入院治療が必要となります。具体的には、BMIが15以下である場合や、心臓、腎臓、肝臓などの重要臓器に損傷が生じた場合、精神状態が不安定である場合などが挙げられます。入院の規定は国や地域によって異なりますが、一般的には医師の判断に基づき、必要性や緊急度に応じて入院が決定されます。治療の目的は、身体的な合併症や栄養状態の改善、精神状態の安定化、摂食障害の症状の改善などが含まれます。治療期間は個人差がありますが、数週間から数か月以上にわたる場合があります。
神経性過食症の治療
神経性過食症の治療法は、食事療法、薬剤治療、心理面の治療があります。それぞれの治療法について詳しく説明します。
- 食事療法
神経性過食症の場合、過食が繰り返されることが多いため、食事制限を行うことが一般的です。ただし、過剰な食事制限は逆効果になることがあるため、栄養バランスの取れた食事を心がけ、適度なカロリー摂取を目指すようにします。また、食事記録をつけることで自分の食生活を客観的に把握し、改善することができます。 - 薬剤治療
神経性過食症の治療には、抗うつ薬や抗不安薬などの精神安定剤が使われることがあります。これらの薬は、過食癖を抑制することで食欲をコントロールし、摂食障害の改善に役立つことがあります。 - 心理面の治療
心理療法は、神経性過食症の治療において非常に重要な役割を果たします。代表的な治療法としては、認知行動療法が挙げられます。この治療法では、過食のトリガーとなるストレスや不安を解消するための技術を身につけ、過食癖を改善することが目的となります。
また、家族療法やグループ療法なども行われることがあります。これらの治療法は、患者自身が自分の問題に向き合い、改善していくためのサポートを提供します。 - 【失コントロール感】
神経性過食症の「失コントロール感」とは、過剰な食事摂取行動を抑えることができず、自分自身が食べ過ぎてしまったという感覚のことを指します。食べ過ぎた後に自己嫌悪や罪悪感を感じたり、自分自身を責めたりすることがあります。このような感覚は、神経性過食症の特徴的な症状の一つであり、過剰な食事摂取を繰り返す原因となることがあります。心理療法や薬物療法など、適切な治療を行うことで、このような症状を改善することができます。
薬物療法
1. 抗うつ薬
- 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI): セロトニンの濃度を調整し、食欲や情動の制御に影響を与えることが期待されます。
2. 脳刺激法
- 深部脳刺激療法 (DBS): 食欲を制御する部位に電極を挿入し、脳の神経回路を調整する治療法です。
3. 作用メカニズム
- 薬物は脳内の神経伝達物質のバランスを調整し、食欲や情動の制御に影響を与えることが期待されます。
4. 効果
- 薬物療法は神経性過食症の症状の改善に効果があることが報告されていますが、個人差があります。
精神療法
1. 認知行動療法 (CBT)
- 概要: 過食のトリガーを特定し、健康的な食事行動を養成する治療法です。
- 効果: 過食行動のパターンを理解し、健康的な摂食習慣を養成することが期待されます。
2. 過食行動防止療法
- 概要: 過食の原因を特定し、具体的な対処法を開発する治療法です。
- 効果: 過食行動の予防や対処策の開発を通じて、症状の改善が期待されます。
併用療法
薬物療法と精神療法を併用することで、食欲の安定と、過食行動への対処法の習得が可能となります。
治療の選択は患者の状態に応じて調整され、患者と治療チームとの協力が治療に重要です。治療計画は患者の症状やニーズに基づいて個別に調整されるべきです。
神経性過食症の胃バイパス手術
【胃バイパス手術】
肥満治療の一つとして、胃の一部を切除する手術があります。この手術は、「胃バイパス手術」と呼ばれています。具体的には、胃の上部を分離して小さな袋状にし、小腸の上部に直接つなげる手術で、食事の量を減らすことができます。この手術は、BMIが40以上の重度の肥満症患者や、BMIが35以上で合併症を持つ患者に行われることが多く、手術後は減量が期待されます。
手術を受け入れるかどうかは、医師の判断と患者の希望によって決定されます。ただし、手術には合併症のリスクがあるため、必ずしも全ての肥満症患者に推奨されるわけではありません。手術を受ける際には、リスクやメリットをきちんと理解した上で決定する必要があります。
過食症・やせ症の具体的治療ステップの解説は2ページ目をご覧ください。